人財教育の実効を上げるために⑨
今回で「人財教育現場で思うこと」の最終回であるが、最後に幣団体が昨年、行った「教育・研修に効果に関する調査」の結果を掲載して終わりとしたい。
下記の調査からも、「経営課題に直結する教育」への関心の高さが窺え、筆者が本テーマの中で長らく訴え続けてきたことが一応検証されているといえるのではないだろうか。
また、御社における「人材教育の革新の方向性」を示めしているともいるのではないだろうか。
参考:教育・研修の効果に関する調査結果
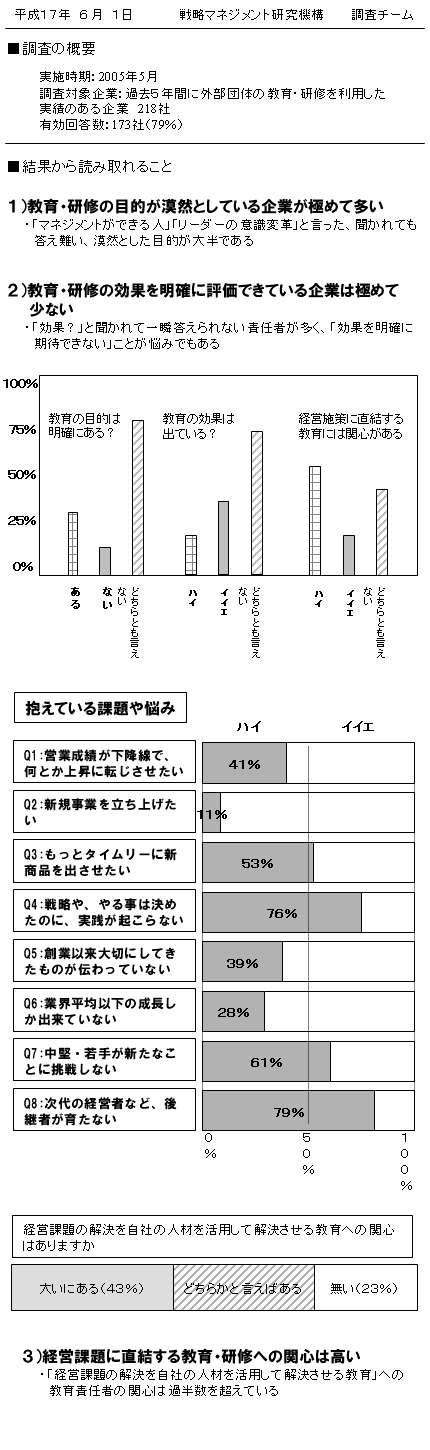
人財教育の実効を上げるために⑨
今回で「人財教育現場で思うこと」の最終回であるが、最後に幣団体が昨年、行った「教育・研修に効果に関する調査」の結果を掲載して終わりとしたい。
下記の調査からも、「経営課題に直結する教育」への関心の高さが窺え、筆者が本テーマの中で長らく訴え続けてきたことが一応検証されているといえるのではないだろうか。
また、御社における「人材教育の革新の方向性」を示めしているともいるのではないだろうか。
参考:教育・研修の効果に関する調査結果
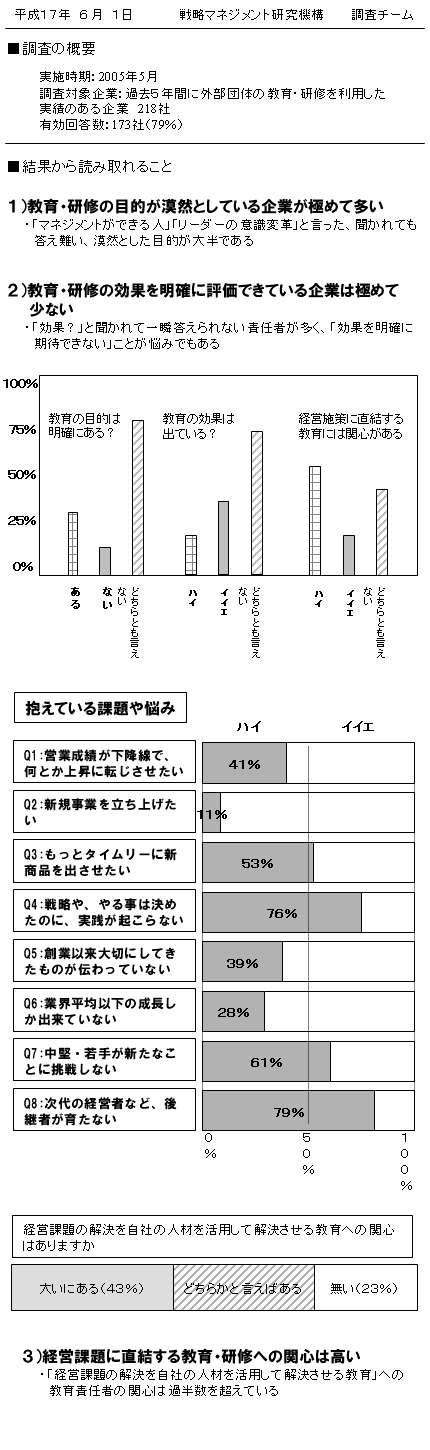
人財教育の実効を上げるために⑧
これまで、人財教育の実効性が上がらない要因として"1.人財像の定義が不明確""2.教育の内容や中身そのものの"問題、そして"3.まずは教育ありき"という考え方に大きな問題があることさらに、"4.教育施策や育成制度がビジネスモデルや経営戦略と全く連動していない""5.組織の規範や風土が新しい知識や情報を阻害""7.講師やトレナーといわれる教育実施者のレベル" "8.経営トップの人材育成への関わり方"等の問題について説明してきた。
最後に
例えば、戦略ひとつとっても教育団体やMBAは、「一般論としての戦略の立て方」は教えてくれても「自社にとって最適となる戦略」は立ててはくれないし、その結果についても一切の責任を負ってはくれないのである。
自社にとって最適な戦略は、自社で構築しなければならないし、その戦略を推進するのも自分達であり、その結果についてのリスクや責任も自分達が負うのである。
自社の経営課題や業務課題等の現実の課題解決や改革案を当事者自らが考え出すというプロセスで人間は生きた学習をし、同時にその体験が成長や育成につながるのである。
そのためには、組織の中に業務遂行機能だけではなく、人を活かして育てる機能を持たせることが重要となる。
経営者の方々や人事部門の方々はこのような視点を持つと共に、教育の投資効果や有効性という観点から自社の人財と人財育成を捉えるべきである。
どんなに優れた制度や最新の設備機器類を導入しても、所詮はすぐ他社に真似される。
真に差別化できるのは人財のみであり、故に人財の革新が企業力に直結するのである。
このような本質的な視点を持つと共に投資効果と実効性という観点から自社の「人財と人財教育」を捉えるべきではないだろうか。
そのために、最大、配慮すべきは、人財を中心とした経営システムを構築することであろう。
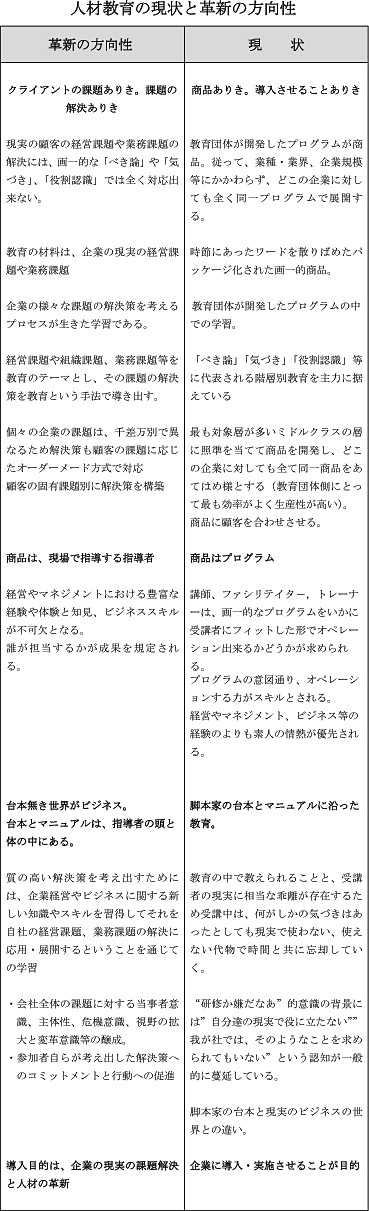
*続きはこちらにどうぞ。
【人財教育現場で思うこと】⑪最終回