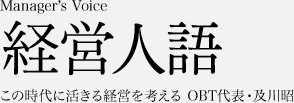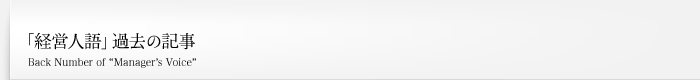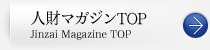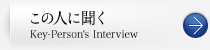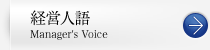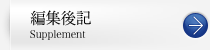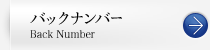OBT 人財マガジン

2010.02.10 : VOL85 UPDATED
-
イノベーションや変革を阻む「組織の能弁さの罠」
日本企業の多くで「イノベーションが生まれない」「新しい事業が創出できない」等
といった話題には事欠かない。
この背景にあるものを考えてみると、かってスタンフォード大学のJeffry Preffer教授が
示したsmart talk trap(能弁さの罠)が思い出されてならない。
「他者の話に批判的にふるまったり、批評したほうが格好よく見える」「能弁さを伴う
批判や懐疑的な意見が、折角のアイデアの実行を複雑・困難なものにしていくという」
という見解である。
我々も、昨今、次世代の経営者養成やビジネスリーダーの育成といったテーマに
関わる機会が非常に多い。
要は、年間、12日間~15日間かけて選抜された参加者を集中的に養成することを
ねらいとしている。
大方の場合、養成の帰結点として「我が社の経営改革案の構築」や「これからの我が社の新規事業構想」等といった類のものを経営陣にプレゼンテーションする場が
設定されている。
そして、1月~3月といった時期になると、受講者達がエネルギーと時間をかけて練り上げた「経営改革案」や「新規事業」のプレゼンテーションの場に担当講師として
招待されることが多い。
その際、経営陣から決まって出るのが、「今の消費者ニーズの傾向はどうなっている
のか」「どこで利益を上げるんだ」或いは「リスクはどこか」等といった質問である。
要は、分析が甘いという指摘であり、これではとても実現不可能という駄目出しである。この場面に接して、私は、この種の企業では、永遠に「組織からの創発」や
「イノベーティブな変革」等は決して生まれず、「企業風土や文化も硬直的で活性化
しない」ということを確信するのである。
然しながら、この種の企業の経営陣に限って、「ウチでは、新商品や新技術が容易に輩出されない」と嘆いている場合が多いのも皮肉なことである。
本来、どのような組織にも新しい事業プランとか、新製品アイデアとか、或いは技術
そのものとか存在しているがそのアイデアが埋没してしまっているのである。
意識の高い人たちがいろいろなアイデアを出すものの、それがうまく利用できず、埋没させてしまう。
大きな問題は、経営陣が本気になるかどうかということ。最終的に判断する経営陣のところで歯止めになってしまう企業と、それがうまく促進
される企業に大きく分かれるのである。
では、何故、アイデアや事業プラン等といったものが実用化出来ないのか、理由と
してはいくつかあると思うが、実は「組織が能弁すぎるから」といえるであろう。
組織が能弁だとどうなるか、というと動けなくなる。
面白い、最初は実用化出来そうな魅力的なプランも能弁さが蔓延している組織ではいろいろな人たちの横やりが入って、結局複雑な実行困難なアイデアとなって
実用化出来なくなってしまう。
能弁というのは、基本的に自信に溢れていて歯切れがいい。情報やアイデアが
ユニーク、語彙が豊富等このような人を通常は能弁な人という。
問題はこういう意味での能弁さというのは、組織の中に蔓延していく。つまり自信に溢れていて歯切れがよく、情報やアイデアがユニークで語彙が豊富な
人ほど、一般的に組織での影響力が強いから出世もしていく。
そして、出世していくから組織の中での発言力も強くなり、このように組織の中に能弁さが蔓延していく。
そうすると何が問題になるかというと、能弁さの中で当初は実行可能なおもしろい
アイデアであったかもしれないものが、いろいろな形で「ここのところ分析したのか」
「最近こういうことが言われているけどその辺はちゃんと検討しているのか」という形で
どんどんくると、次第に当初のアイデアは、実行困難なものに姿を変えてしまう。
この能弁さの罠という現象は、優れた企業、大企業といわれる企業ほど蔓延して
いく傾向にある。
そうなるとアイデアや提案があっても結局埋没していってしまう。
「能弁さの罠」が蔓延している組織では、会議の前日は、売り上げや販売の動向、
消費者調査などを分析し、データ処理した資料づくりに追われる。
経営会議では分厚い分析資料やスクリーンに映される分析データなどをもとに、「市場分析から導き出される商品は......」と、次の商品開発が検討される。
こういった光景が非常に多いのである。ビジネスや事業に関わる多くの人々が分析マヒ症候群に陥り、いくら分析を重ねても、
市場の真実や顧客の実相が見えず、誰もがただ疲弊していく。
これが多くの日本企業が昨今直面している現状だろう。また、「今の時代は顧客のニーズに合った商品を提供することが重要であり、顧客
ニーズがどこにあるかを知るためにも、競合の動向を把握するためにも、十分な市場
調査を行い、分析をすべきである」等と大した実践の経験も無いMBAチックなフレーム
ワークを駆使して如何にもわかっているようになっている若手社員が事の他多い。
そして、分析結果をもとに判断し、実行しても思うように成果が出ないと、分析のもとになったデータに責任を転嫁したり、現場の意欲の無さに転嫁したりする。
この状況は、全く笑止千万で滑稽ですらある。ヒット商品や成功した事業で、市場分析や市場調査から生まれたものがどれだけ
あっただろうか。
これまでにない全く新しい商品、市場、業態を生み出したり、既存の常識を覆す発想で
事業を再構築したり、顧客に対して新しい価値を提供したものばかりある。
新たな知識創造は、単なる市場分析からは決して生まれない。
むしろ、どんなアイデアでも提案でも真剣に考えていこうというカルチャーから生まれる
のである。
ひとつは、
単に批判するだけでなく、建設的な批判になっているかどうか。
つぶすための批判と、それをうまく実行させるための批判、代替的なアイデアを出しながらの批判とでは、いいものがちゃんと出ていくか、出ていかないかでは随分違う。
もうひとつは
新しいアイデアが実用化できないというのは、それを正当化できないことにも関連している。そのためには、実践を学習の機会ととらえるような仕組みやカルチャーを作るこ
と。とにかく試行錯誤して考えながらやっていく。
いずれにしてもアイデアや知が実用化できないということは、組織の将来にとって
致命的な欠陥となっていくことは疑いも無い。
この種の企業が存在意義を問われ、市場における必然性を次第に喪失していく
のである。
On the Business Training 協会 及川 昭