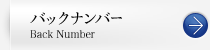OBT 人財マガジン

2008.01.30 : VOL38 UPDATED
-

株式会社一ノ蔵
マーケティング室室長 山田好恵さん
伝統のものづくりに学ぶ、オンリーワンの競争力とは(前編)
昭和30年には4021場あった清酒メーカーは、平成17年には1737と、往年の4割近くにまで減少しています。一部の大手メーカーによる寡占が進み、極端な価格競争の波に飲まれて個性的な中小の事業所が姿を消していく。この現象は、他の産業にも共通なものといえます。その中にあって「オンリーワン」を目指し、清酒の復興に賭ける企業があります。時代の波に流されずに本物を守り続けられる強さの秘けつとは。一ノ蔵マーケティング室室長、山田好恵さんに伺ったインタビューを、前編・中編・後編の3回シリーズでご紹介します。
-
株式会社一ノ蔵 (http://www.ichinokura.co.jp/)
宮城県にあった4つの酒蔵、浅見商店・勝来酒造・桜井酒造店・松本酒造店が企業合同して昭和48年に誕生した清酒メーカー。機械化すれば6名前後の蔵人で生産可能な3万石の蔵に48名の蔵人を配し、「良い米を使い、手間暇をかけ、良い酒を造る」という姿勢を貫く。昭和52年には良い酒を安く提供するために、あえて級別監査(現在は廃止)に出さず2級酒として発売した本醸造酒「無監査」がヒット。以来、こだわりを貫く酒蔵として清酒ファンの支持を広く受ける。
YOSHIE YAMADA
1964年生まれ。86年に、大卒の新卒社員一期生として株式会社一ノ蔵入社。物流企画課に配属になり、入社したその年に、女性向けの低アルコール酒「ひめぜん」の開発を任せられ、ヒット商品に育て上げる。05年に現職に就任。
-
4社が企業合同して、「一ノ蔵」が誕生。
平等主義を貫き、4社合同の組織をまとめあげる。──御社は1973年に4社の酒造メーカーが企業合同するという形で創業されました。創業後の滑り出しは、順調だったのでしょうか。
いえ、やはり最初の10年間はものすごくギクシャクしたらしいです。企業合同という姿についていけない人たちもいて、当時の蔵人の中には辞める人もいたと聞いています。それまでは、自分のところの社長だけを見て仕事をしてきていますので、急に「社長ではなく副社長になった」といわれても従えないわけですね。でも、そういう悪しき習慣といいますか、過去の習いはここ15年ぐらいですっかりなくなりました。
経営者自身が「自分たちの会社」ではなく、「わたくしたちの会社」「みなさんの会社」ということをずっと言い続けてきて、みんなの中に「アワーカンパニー」という意識が生まれてきたのだと思いますね。
※高度成長期を経た1970年代から80年代にかけてのこの時期は、ウィスキーやビールの台頭により清酒需要に陰りがみられるようになり、「大量生産、大量消費」の風潮の中で、地方の中小の酒蔵は苦戦を強いられていた。その中、地酒の生き残りをかけた4つの酒蔵の企業合同により、一ノ蔵は誕生した。
────「みなさんの会社」というのは、具体的にはどのようなことなのでしょうか。
創業役員は4人おりますが、それぞれ個性も能力も違いますから、抜きん出て優秀な経営者が長期間に渡って社長を務めることがあってもよさそうなところを、町内会の会長さん選びみたいに4年任期で社長を交代していくんですね。すごく平等だなと思います。
そうすることによって、「みんなに機会を与える」とか「一人だけのものにしない」といった風土が根付いたのではないかと思うんです。1社、絶対的に強いところがあったというわけではなくて「みんな平等」で始まっていますので、そういう平等感が社風の一つにある。「チャンスはみんなで分ける」という雰囲気があるんですね。
伝統を守った手作りの酒造り。
理念を貫くことが競争力の源泉に。────「伝統の手造り」を貫かれていることも、創業以来のこだわりだと伺っています。

そうですね。そもそもは、東北地方というのは地元の酒を飲むという文化がある地域でしたから、いうなれば自分たちの地域、自分たちの市町村で飲んでもらえれば、十分に経営は成り立っていたわけです。けれども一ノ蔵が創業した当時は、大手の酒造メーカーがテレビコマーシャルで攻勢をかけ、東北の小さな町や村にまで大手の銘柄が入ってきて地酒が次々と淘汰されていく厳しい時代がスタートしたころでした。資金力でも宣伝力でも、とても大手にはかないません。だったら、大手にはできない手造りで心をこめた酒を造ろうと。そして「オンリーワン」になろうというのが、一ノ蔵のもともとの発想なんです。
ですから、経営者からは「どんな時代になっても品質へのこだわりだけは捨てるな」といわれてきました。とにかくこだわって、いいものを作り続ける。そうしてできあがったものがわれわれの唯一の宝なんだということを、一人一人が本当によく理解していると思います。

今では多くの清酒メーカーで機械化されている作業も、一ノ蔵では頑なに伝統の手作業を守っている。写真は、醪(もろみ)の仕込み風景。(写真提供/一ノ蔵)
────昭和52年に日本酒の階級別制度の挑戦として「無監査」という商標の清酒を発売されましたが、これも「オンリーワン」を象徴していますね。
いいお酒を作って高い値段で売るというやり方はあまりにも当たり前ですし、それは消費者の立場に立って考えるとメーカーのエゴだというのが、創業者の考えなんですね。お客さまに喜んでいただける良いお酒を作るためには、あえて監査を受けずに酒税が安い二級に甘んじる方法があるということに鈴木(創業者の一人である鈴木和郎氏。故人)が気づきまして、「無監査」という商標を取って出したわけです。税務署ともずい分喧嘩をしたらしいんですが(笑)、この考えが日本酒通の方々にいたく共感いただき、「無監査」は全国的なヒット商品に成長しました。

今では多くの清酒メーカーで機械化されている作業も、一ノ蔵では頑なに伝統の手作業を守っている。写真は、醪(もろみ)の仕込み風景。(写真提供/一ノ蔵)
その後、平成4年に級別制度はなくなりましたが、「無監査」という商標で引き続き出しています。もう級別がないわけですから、無監査も何もあったもんじゃないとも思うんですけども、これはやはり一ノ蔵が伸びる起爆剤になった商品。安くてよいものを提供するという当社の弊社のこだわりを象徴するものでもありますので、今後も継承されなければいけない商標だと思っています。
「一ノ蔵 無監査本醸造」:1977年発売。知名度の低さで業績が低迷していた一ノ蔵が、創業4年目に起死回生をかけて発売した商品。清酒を特級から二級にまで種別していた当時の級別制度を逆手に取り、あえて監査を受けずに二級酒として発売。酒税が低く抑えられることで高品質の酒を低価格で提供でき、ヒット商品となった。(写真提供/一ノ蔵)
現場主導で開発した商品がヒット。
社員の間に自主性が生まれる。
「ひめぜん」※写真は2008年1月現在。3月にリニューアルを予定
アルコール分8%の低アルコール酒。すだちやかぼすを思わせる柑橘系の香りが女性客を中心とする日本酒の初心者に支持され、1988年の発売以来、ロングセラー商品となる。(写真提供/一ノ蔵)────山田さんは1987に入社されてすぐ、女性向け低アルコール酒の商品企画を手がけられたそうですね。
「ひめぜん」ですね。女性にとって、飲みやすい、買いやすい、持っていって恥ずかしくない、もらってうれしいようなものは何なのかと考えてつくった商品です。
────入社後すぐに新商品の企画を任されたというのは、すごいですね。

私が入社した当時は創業してまだ十数年の、ようやく会社としてまとまりができてきた、非常に伸び盛りの段階でしたので、新商品をつくる専従者を育てていこうという考えがあって新卒の採用計画を進めていたんですね。ですから配属された物流企画課はまったく新しい新設の部署で、女性の先輩社員もいませんでした。
けれども入社してみましたら、やはりこの業界はものすごく古いんですよ。男社会ですし、新しいものを作るといっても、なかなか難しいものがある。けれども何かの飲み会のときに、当時発売したばかりだった低アルコールのお酒(「あ、不思議なお酒」)を「うちも女性向けのこういうお酒を作っているんだよ」と注がれまして。それがあまりにもおしゃれではなかったものですから(笑)、「これでは売れないのではないですか」という話をしましたら──事実、売れていなかったのですが──、恐らく経営者はカチンときたんでしょうね(笑)。「それなら、商品を開発してみろ」といわれて担当することになりました。
────商品のコンセプトは、どのようにして固めていかれたのですか。
そのころは「ものを売るにはストーリー性が必要だ」といわれていましたので、それならば、宮城の一ノ蔵を売り出していくために「宮城県」ということを連想できるものにしようと。ちょうど当時、伊達正宗の話が大河ドラマになっていたときでしたので(※)、伊達正宗に関係することで、しかも女性に関わること、伊達正宗の奥方だった愛姫(めごひめ)に通じるストーリーを考えようと考えたんです。
※1987年1月4日〜12月13日に放送の「独眼竜政宗」
愛姫は12歳で山形から輿入れしています。まだ子どもですから、お父さんやお母さんが恋しいといって泣くんですね。その姿を見て、自分自身もまだ13歳だった正宗が、非常にかわいそうに思うんです。そして愛姫なぐさめるために朱塗りのままごとの道具「お姫様御膳」を贈った。その「お姫様御膳」から取ったのが「ひめぜん」という名前です。「なぜ「ひめぜん」というのですか」と聞かれたときに、正宗と愛姫の話にまでふくらませてお客様に伝えることができるということが、発想の一つにあったんですね。
もう一つ、「ひめぜん」の開発では、コンセプトを「ネオクラシカル」という風にしました。酒造りの技術というのは。室町時代に完成に近い姿を見るのですが、当時は環境も整っていませんでしたので、今のように18度、19度まで発酵しなかったんですよ。せいぜい12、13度くらいで発酵が止まっていた。そこで、低アルコール酒は室町時代のお酒に似ているということで生まれたコンセプトが「ネオクラシカル」。そこに、実際にあった過去の話である「お姫様御膳」を重ねて、「ひめぜん」という商品を考えたわけです。
当時の社長でありました鈴木に「こういう風に考えているのですが、どうでしょうか」と話しましたら、「それでいこう」と。「後は好きなようにやりなさい」といわれましたので、容量はどうしようか、ボトルの形状は、という風に進めていきました。
「ひめぜん」は500mlのボトルを採用していますが、この容量のお酒というのはお土産用として一部あるくらいで、当時はそんなにありませんでした。けれども720 mlでは女性が一人で飲むには持て余してしまう。500mlならボトルの背も高くないのでテーブルに置いても邪魔にならないということから、容量は500mlにしようと。
実は、ワインで女性のお酒に対する門戸がずいぶん広がったので、「ひめぜん」の前身となった「あ、ふしぎなお酒」のボトルも当初はワイン風のデザインでした。けれども、一ノ蔵は日本酒なのだからワイン風にすることはないだろうと思ったんですね。もっと和風のシンプルな作りにして、金や白、赤などの色づかいだけでやりましょうと提案して、今現在のラベルになりました。
────男社会といわれる風の中で、入社したての女性が新商品を開発することに対する、社内の反応はいかがでしたか。

「ひめぜん」は、発売と同時に好調な売れ行きを見せ、低アルコール酒の市場を開拓する先駆け的な商品となった。「八八年十月に売り出すやたちまち売り切れというありさま。二年目以降もずっと二桁の伸びを示すヒット商品になった。」(「オンリーワンの蔵」今井亮平氏著 ブレインキャスト刊 より引用)
仕事はものすごく楽しかったのですが、周りの先輩からすれば面白くない存在であったとは思います。ずいぶん、鼻っ柱をへし折られました(笑)。けれども、そういう経験も今となってはとてもありがたいことだなと思えるようになりましたし、経営者は新人を育てるということも想定しながら仕事を託したのかなという風にも思うんですね。
────「ひめぜん」がヒットしたことで、社内にも何か変化は起こりましたか。
「ひめぜん」のヒットをきっかけに、企画を社員に任せるということを役員自身ができるようになり、それを社員が受けて、形にしていこうと自主的に動くことができるようになってきたのではないかと思うんです。
「ひめぜん」はプロモーションも工夫していまして、テレビコマーシャルにでも乗せれば、もしかしたらあっという間に広がったのかもしれませんが、地酒ですからナショナルブランドと同じようなことはするまいと。お客さまの口コミによって商品が伝播していく、その力を信じようと考えまして、発売するときには「『ひめぜん』パーティー」というのを、特に大きな宣伝もせずにやったんですね。200名ぐらいの方が集まったでしょうか。
パーティーでは、仙台で活躍している料理研究家2人に「『ひめぜん』に合う和食」「『ひめぜん』に合う洋食」と、それぞれテーマを持ってテーブルコーディネートをしていただいて、「なぜこの料理が『ひめぜん』に合うのか」をプレゼンテーションしてもらったんです。そして、お客様には実際にそのテーブルまで降りてきていただいて、試食していただくというようなことをしました。
「ひめぜん」のこのパーティーは、規模は非常に小さいものでしたが、新商品を出す時には発表会をすべきだいうことが社内で認識できたものですから、その後に出された商品では、ホテルを借り切ってパーティーをするということが定着しました。そのときの企画も、役員が社員に任せるんです。

「大和伝」宮城県松山町の刀匠 法華三郎信房氏(県重要無形文化財指定)の伝える「大和伝」から命名。名刀大和伝のごとく鍛え上げ、蓋麹での製麹、低温発酵と造りにこだわり抜いた酒。(写真提供/一ノ蔵)
例えば「大和伝」という商品を出したときには、刀鍛冶の方に来ていただいて実際に刀を展示して「なぜこの刀が酒になるのか」というようないわれを説明したり。大きな生け花のパフォーマンスを取り入れたパーティーをしたこともあります。「お酒を飲んで美味しかった」というだけではなくて、お酒プラスαで強く印象づけるということを社員が考えるようになったんですね。
────そういった体験を通して、社風も徐々に変化してこられたのですね。
そうですね。「絶対的な経営者と従業員」というそれまでの関係図から、「会社を動かしていくのは、われわれ社員にもできるんだ」ということが何となくできあがってきたのかなという気がするんですよ。旗振り役の経営者だけが社員を引っ張るのではなくて、社員も一緒に会社を動かしていくということの動機づけになったような気が、私はしてるんですね。
創業から30年を経てなお、伝統の酒造りを守る一ノ蔵。創業の精神を、ブレることなく貫き続けられるのはなぜなのか。中編では、一ノ蔵の経営理念や人材の採用・育成について伺います。
*続きは中編でどうぞ。
伝統のものづくりに学ぶ、オンリーワンの競争力とは(中編)
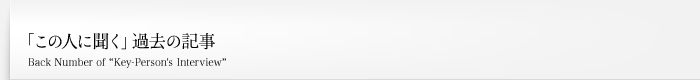
- 株式会社JR東日本テクノハートTESSEI
専務取締役 矢部 輝夫さん - 【事業で差別化しうるのは唯一人財のみ】
企業改革を阻む制約をいかに克服するか(前編) - 千葉夷隅ゴルフクラブ
総支配人 岡本 豊さん - 【事業で差別化しうるのは唯一人財のみ】
見えざる資産を競争優位にするために必要なこと(後編) - 千葉夷隅ゴルフクラブ
総支配人 岡本 豊さん - 【事業で差別化しうるのは唯一人財のみ】
見えざる資産を競争優位にするために必要なこと(前編) - 七福醸造株式会社
代表取締役会長 犬塚 敦統さん - 【事業で差別化しうるのは唯一人財のみ】
人が気づき、変わる瞬間とは(後編) - 七福醸造株式会社
代表取締役会長 犬塚 敦統さん - 【事業で差別化しうるのは唯一人財のみ】
人が気づき、変わる瞬間とは(前編) - 株式会社キングジム
代表取締役社長 宮本 彰さん - 【事業で差別化しうるのは唯一人財のみ】
知というアイデアを製品化し、利益に結びつける組織とは(後編) - 株式会社キングジム
代表取締役社長 宮本 彰さん - 【事業で差別化しうるのは唯一人財のみ】
知というアイデアを製品化し、利益に結びつける組織とは(前編) - 東海バネ工業株式会社
代表取締役社長 渡辺 良機さん - 【事業で差別化しうるのは唯一人財のみ】
やること、やらないことを決める
競争優位を明確にすることは、社員育成にもつながる(後編) - 東海バネ工業株式会社
代表取締役社長 渡辺 良機さん - 【事業で差別化しうるのは唯一人財のみ】
やること、やらないことを決める
競争優位を明確にすることは、社員育成にもつながる(前編) - 人とホスピタリティ研究所所長
前リッツ・カールトン日本支社長
高野 登さん - 【事業で差別化しうるのは唯一人財のみ】
成熟化社会は、ホスピタリティが鍵となる(後編)