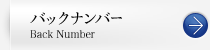OBT 人財マガジン

2010.06.09 : VOL93 UPDATED
-

株式会社永楽屋
代表取締役社長 細辻 伊兵衛さん
【長寿企業研究】
起点は「自社事業の検証」。
倒産危機から経営を立て直し、創業約400年の事業を存続(前編)「老舗企業の歴史は変革の歴史」と言われるが、京都の老舗織物商、永楽屋もその一社だ。代々、太物商(綿・麻の織物商)を営んできた家業を戦後にタオル卸に転換。しかし、海外のライセンスブランドに太刀打ちできずに倒産の危機を迎え、1999年に事業の大改革に踏み切る。再建を目指していた細辻社長は昔、自社で作っていた「手拭い」に事業立て直しの糸口を見出す。「現代のどんなに素晴らしいアーティストとは一味違った」魅力を感じたという。周囲からの反対を押しのけ、従前の様に汎用品/仕入品ではなく"自社発"老舗ブランドを立ち上げ、復活を遂げた。時代の流れとともに市場、競合、顧客が変わり、企業が提供できる付加価値も変わる。経営リーダーに求められることは環境変化に照らして自社事業を検証できる客観的な視点である。
『長寿企業特集』第三回目は、永楽屋十四代当主・細辻伊兵衛さんにお話を伺います。 -

永楽屋本店(画像提供:永楽屋)
株式会社永楽屋 ( http://www.eirakuya.jp/)1615年創業。創業家の先祖が、戦国時代に永楽通寳の紋を使用していたことから、屋号を『永楽屋』とする。代々、"太物"と呼ばれる木綿・麻の織物を扱い、第二次世界大戦後にタオル卸業に業態転換。全国有名百貨店との取引を広げるが、ライセンスブランドを持たなかったことから業績が悪化。1999年には債務超過に陥り、倒産の危機を迎える。同年に十三代当主が引責辞任し、十四代細辻伊兵衛氏が代表取締役に就任。明治から昭和初期にかけて同社が扱っていた手拭いを復刻し、2000年に『京三条町家手拭「永楽屋 細辻伊兵衛商店」』を再開。自社ブランドを立ち上げたことで経営の再建を果たす。2004年からは多ブランド化に乗り出し、新感覚の手拭いブランド「RAAK(ラーク)」、帆布鞄専門店の「伊兵衛 Ihee」、風呂敷専門店の「伊兵衛 ENVERAAK」ほかを展開。
企業データ/資本金:2600万円、従業員数/100名、店舗数/22店(2010年5月末現在)IHEE HOSOTSUJI
1964年生まれ。高校卒業後、卓球の実業団選手として大手自動車メーカーのグループ企業に入社。1985年にアパレル業界に転身し、海外系ブランドの店長として高い業績をあげる。1991年に永楽屋十二代当主の長女と結婚して永楽屋に入社、翌年に十二代当主が急逝。叔父が十三代目を務めた後、1999年に十四代細辻伊兵衛を襲名し、代表取締役に就任。
-
自社の"個性"を打ち出せなかったタオル卸時代
────細辻社長は27歳で永楽屋さまにご入社されましたが、会社にはどのような第一印象を持たれましたか。
まず感じたのは、自社の独自性を打ち出すことが難しい事業だということですね。当時はタオルの卸売業が主力事業でしたが、タオルは手拭いと似ているようでいて、実はまったく異質な事業です。商品の需要というのは"自家需要"と"進物需要"に分かれるのですが、当時のタオル業界は"進物需要"がほとんどでした。これの何が難しいかといいますと、進物というのは体裁が重視されるんですね。贈った相手の方に「良いものをいただいた」と思っていただける体裁が大事になる。つまり、ブランドもののタオルが重宝されるわけです。なおかつ、デザインの個性が強すぎてもいけませんから、多くの方に好まれるものが売れていくんですよ。
しかし、当時の私は"自家需要"や"進物需要"という言葉すら知らず、前職のアパレルと似たような業界かなという程度の考えでいたわけです。「これからは、タオルでファッションや」と。しかし入ってみたら、ファッション業界とは違う世界でした。
むしろ逆に、異質な存在は私の方だったかもしれません。その頃の私は、髪を金髪に近い色に染めて、当時流行りのベルサーチのネクタイを締めていったりしていましたので(笑)。今は京都らしくしていますが(笑)、17、18年前はそんな感じで周囲の反発を買ったこともありましたし、何かを言うにしても、業界をよく知らないままでは理解してもらえない。ですから、まずは既存のお取引先にタオルの営業に行き、問屋さんの勉強をすることから始めたんです。
────まずは事業の仕組みを知ろうということですね。
ええ。ただ、例えば"バーバリー"といった強いブランドがあれば、自信を持って営業できますが、当社にはそういったライセンスブランドがありませんでした。商品といえば、ノーブランドの無地のタオル。非常に売りにくかったんですね。タオルで会社を再生させることは、非常に時間がかかると考えました。それを確信した経験でした。
本家を売却し、会社の再建に乗り出す
────その後、1999年に14代当主として永楽屋を継承され、事業の大胆な改革に乗り出されました。

私が永楽屋に入社した翌年に、12代当主の義父が急逝しまして。叔父が13代目として代表取締役に就任したのですが、事業を立て直すことができず、ついに債務超過になってしまったんです。永楽屋は代々、本家が株のほとんどを所有しますから、何かあったときには家長である私が責任を取ることになります。それならば、経営の舵も自分の手でとりたいと考えたのです。
そこでまずは、本家(自宅)を売却して、事業再建の元手を作りました。土地建物だけでなく蔵にあった古道具も全部売って、仏壇は大きすぎてマンションには入りませんでしたので、お寺に預かってもらいました。そのうえで、叔父に「辞めていただきたい」と退任を迫ったのです。会社の財務がそこまで悪化していたということと、私が本家の売却にまで踏み切ったことで、叔父も当時の役員の方々も、みなさん辞める気になっていただいたようです。
────歴史のある本家を売却されることに、迷いはありませんでしたか。
まったくありません。会社は社員の給料も払えないような状況だったんです。周囲には反対されましたが、本家は私が家長として受け継いだもの。決断に迷いはありませんでした。結果として、売却で得た資金を退職金に充てて当時30名いた社員を7名にまで減らし、借入金も返済して身軽になった。じゃあ、これからは自分が納得のいく事業をやろうと。そう考えて始めたのが、明治から昭和初期にかけて当社がつくっていた手拭いの復刻だったのです。
不可能に挑戦した"老舗ブランド"復活への道
────社長ご就任時には、手拭い事業の立ち上げを決めておられたのですか。
いいえ、そのときはまだ何も考えていません。"復刻"なんて、そんなにすぐに思いつきませんよ(笑)。簡単に思いつくんやったら、先に誰かがやっているはずでしょう。ただ、気にはなっていました。本家の売却で倉庫を整理していたときに昔の手拭いが出てきまして、非常に多くの絵柄が残されていたんです。ああ、永楽屋にはこんな面白いものがあるやないかと。そして、一日の業務が終わってから手拭いを写真に撮って、関連する資料を調べるということを毎日続けていたんです。
────なぜ、手拭いが気になられたのですか。
明治、大正、昭和とそれぞれの時代につくられた柄は、どれも時代背景を物語っています。それは、その当時に生きていないとわからないことなんですね。現代のどんなに素晴らしいアーティストとは一味違ったものです。つまり、"老舗"であることが活かせるわけです。そうして次第に、この手拭いを"老舗ブランド"にして、何かできないかなと思うようになっていったんです。
────手拭いの染色に使う原版なども残っていたのですか。
いえ、版はございません。残っていたのは、手拭いの現物だけです。ですから、忠実に復刻するためにはどうするかということが問題になりました。昔はPL法(製造物責任法)といった法律もありませんから、色落ちするような染料も使っていたんです。それでよかった時代なんですね。でも、今は違います。高品質で安定したものづくりをしていかなくてはいけない。また、昔は着物という事業の柱がきっちりとありましたので、手拭いは趣味程度につくっていたものでした。それを事業の採算ベースに乗せるのも非常に困難なことで、周囲からは「無理や」といわれたんです。できるのやったら、みんなやってるはずですからね。現に、百貨店さんなどにも興味を持っていただいて、手拭いを見に来られたこともありましたが、誰も手をつけませんでしたのでね。
────その難題を、どう解決されたのですか。
新しい技術を開発していこうという考え方です。不可能を可能にしようと思ったんです。それが"ブランド"ですから。そこでまずは、染織業界のトップクラスの職人や技術者の方々にお会いして、手拭いの復刻に何とか協力してもらえないかと。そういう話からスタートしました。
────すぐにはお取引いただけないこともあったと伺っています。
当初は、京都の老舗だということを前面に打ち出していたのですが、どうもそれが胡散臭かったようです(笑)。それに、職人さんは話すことが得意でない方も多くて、理路整然と説明しても通らないこともあるんですね。私自身が、アパレル業界に入る前は部品メーカーで工員をしていましたから、技術者の方の気持ちはわかるような気がします。それをお互いお話し合いをし、「この人と付き合ってもいい」と思ってもらえるかどうか、なんですよ。
────そのためには、どのようなことが大切になるのでしょうか。
契約の透明性を高めて、「永楽屋の仕事ならしてもいい」と思われるような取引をするということです。また、なるべく高く買うということも、すべてそうできているわけではありませんが、心がけています。普通は値切るでしょう。でも、その会社が困っておられたら、私は言い値で買います。といっても、みなさん正直な方ばかりですので、極端に高い値段はつけないんです。言われる値段は、それがなかったらやっていけないという話。それを叩いたところでね...。
────しかし、繊維業界ではその"業者叩き"が起こっています。
だから、みんな中国に行ってしまったんですよ。そして、日本のものづくりがなくなってきて、えらいことになってるんです。では、どうすればいいかといえば、"限定したものづくり"しかないんです。
 *
*
昭和初期の柄を再現した"復刻版"の手拭い。当時の永楽屋では、毎年百種類の色柄の手拭いを発表する頒布会「百いろ会(ももいろかい)」を主催し、染色の最高技術を注ぎ込んだ数々の名品が生み出された。(写真左「月夜の舞妓[昭和8年]」、右「私は昔『桃太郎』と云われてました[昭和7年]」、画像提供:永楽屋)
 *
*
現当主である14代細辻伊兵衛氏が発表した新柄の手拭い。糸も、手拭いでは通常使わない番手の細いものを使用し、きめ細かな生地を実現。染色は、細やかな絵柄を表現できる友禅染。すべて職人の手作業で染められている。(写真左「すだれ朝顔」、右「鯉」、画像提供:永楽屋)
タオルの卸業から、手拭いの自社ブランド立ち上げへ。「事業転換の明確な道筋が、最初から見えていたわけではない」と細辻社長は話しますが、"稀少価値のある高品質な商品だけを扱う"という信条は、一貫して経営の根底に流れています。信条は曲げずに、戦術は柔軟に。後編では、細辻社長の"変化の経営論"を伺います。
*続きは後編でどうぞ。
長寿企業研究──起点は「自社事業の検証」。
倒産危機から経営を立て直し、創業約400年の事業を存続(後編)
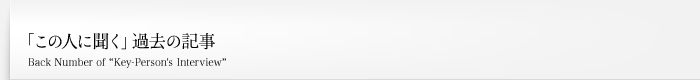
- 株式会社JR東日本テクノハートTESSEI
専務取締役 矢部 輝夫さん - 経営改革は、実行する「現場の実態」を把握して、初めて実現する(前編) - 千葉夷隅ゴルフクラブ
総支配人 岡本 豊さん - 企業の競争優位性は結果指標ではなく
それを生み出す組織の強さ、社員のモチベーションに規定される(後編) - 千葉夷隅ゴルフクラブ
総支配人 岡本 豊さん - 企業の競争優位性は結果指標ではなく、
それを生み出す組織の強さ、社員のモチベーションに規定される(前編) - 七福醸造株式会社
代表取締役会長 犬塚 敦統さん - 【事業で差別化しうるのは唯一人財のみ】
人が気づき、変わる瞬間とは(後編) - 七福醸造株式会社
代表取締役会長 犬塚 敦統さん - 【事業で差別化しうるのは唯一人財のみ】
人が気づき、変わる瞬間とは(前編) - 株式会社キングジム
代表取締役社長 宮本 彰さん - 【事業で差別化しうるのは唯一人財のみ】
知というアイデアを製品化し、利益に結びつける組織とは(後編) - 株式会社キングジム
代表取締役社長 宮本 彰さん - 【事業で差別化しうるのは唯一人財のみ】
知というアイデアを製品化し、利益に結びつける組織とは(前編) - 東海バネ工業株式会社
代表取締役社長 渡辺 良機さん - 【事業で差別化しうるのは唯一人財のみ】
やること、やらないことを決める
競争優位を明確にすることは、社員育成にもつながる(後編) - 東海バネ工業株式会社
代表取締役社長 渡辺 良機さん - 【事業で差別化しうるのは唯一人財のみ】
やること、やらないことを決める
競争優位を明確にすることは、社員育成にもつながる(前編) - 人とホスピタリティ研究所所長
前リッツ・カールトン日本支社長
高野 登さん - 【事業で差別化しうるのは唯一人財のみ】
成熟化社会は、ホスピタリティが鍵となる(後編)