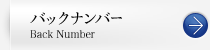OBT 人財マガジン
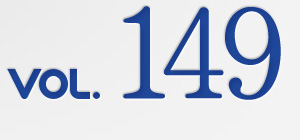
2012.10.10 : VOL149 UPDATED
-

人とホスピタリティ研究所所長
前リッツ・カールトン日本支社長
高野 登さん【事業で差別化しうるのは唯一人財のみ】
成熟化社会は、ホスピタリティが鍵となる(前編)モノやサービスが溢れ、経済が成熟化した今、顧客と強い絆を結ぶ鍵は何か。今回はその手がかりを求めて、前リッツ・カールトン日本支社長の高野登さんにお話をうかがいました。リッツ・カールトンはホスピタリティを中心とした理念を掲げ、独自のブランドを築き上げたことで知られるホテルです。顧客の心に徹底して寄り添うその企業姿勢には、あらゆる業界に通じる貴重なヒントが潜んでいます。現在は、人とホスピタリティ研究所所長としてホスピタリティに基づく生き方を提唱する高野さんに、これからの時代に求められる人と組織のあり方について語っていただきました。(聞き手:OBT協会代表 及川 昭)
-
[及川昭の視点]

長い間、いろいろな企業で組織変革や競争優位作りなどにかかわっていて思うことがある。例えば、競争優位=差別化だとすると、どんなに頑張っても昨今は機能面だけで違いを出すというのは極めて難しくなってきている。 そうすると結局行きつくところは、サービス業はもとより、製造業、流通業、或いは医師や弁護士といったある種の専門性を持っている人達でも「ホスピタリティ」的なものが、その優位性や差別化という意味でも重要な能力となってくる。
高野登氏が、「ホスピタリティとは、OSである」と仰っているとはとても納得感がある。聞き手:OBT協会 及川 昭
企業の持続的な競争力強化に向けて、「人財の革新」と「組織変革」をサポート。現場の社員や次期幹部に対して、自社の現実の課題を題材に議論をコーディネートし、具体的な解決策を導き出すというプロセス(On the Business Training)を展開している。 -
NOBORU TAKANO

1953年生まれ。プリンス・ホテルスクール(現日本ホテルスクール)卒業後、渡米。NYプラザホテル、LAボナベンチャー、SFフェアモントホテルなどの名門ホテルでマネジメントを経験し、1990年にザ・リッツ・カールトン・サンフランシスコの開業に携わる。1994年にリッツ・カールトン日本支社長に就任。1997年にザ・リッツ・カールトン大阪、2007年にザ・リッツ・カールトン東京の開業をサポート。2009年に退社し、長野市長選に出馬するも651票差で惜敗。同年、人とホスピタリティ研究所を設立し、日本各地で人財、組織、地域づくりのサポートを行っている。『リッツ・カールトンが大切にするサービスを超える瞬間』(かんき出版)など著書多数。2012年8月に『リッツ・カールトンと日本人の流儀』(ポプラ社)を上梓。
-
小手先の顧客主義ではなく、企業の根幹として
ホスピタリティを根付かせることが、競争優位につながる────今日は「ホスピタリティ」について、高野さんの今までのご経験からくる知見やご見解をお聞きしたいと思っています。といいますのは、2006年のことでしたがダニエル・ピンク(※)の著作『ハイ・コンセプト』で出会った言葉が、私の心に残っているんです。物質的な豊かさが満たされた社会では機能性よりも、「美しさや精神性、感情といったものに、より大きな価値が見出されるようになる」と。私どもは、さまざまな企業の組織変革や競争優位強化に関わらせていただいていますが、そうした中でもやはり、特に日本企業は機能面での差別化は限界に達しているように感じます。では何が問われるかといえば、精神的な豊かさを生み出す 「ホスピタリティ」が鍵になるのではないかと。これはサービス業だけでなく他の産業も然り、あらゆる仕事でホスピタリティ的なものが間違いなく必要になってくる。こうしたことについて、高野さんはどうお考えになられますか。
※アメリカの作家・ジャーナリスト。アル・ゴア副大統領の首席スピーチライターなどを経てフリーに。『ワシントン・ポスト』などで経済動向やピジネス戦略についての記事や論文を執筆している。
リッツ・カールトンが言い続けてきたのは、「ホスピタリティとサービスは別物である」ということです。例えば「サービスを突き詰めた先にホスピタリティがある」、もしくは「これからはサービスではなく、ホスピタリティを付加価値として強化しよう」といった捉え方をしてしまいがちですね。それは本来のホスピタリティではないということを、リッツ・カールトンはずっと言い続けているのです。
ホスピタリティとは、人の生き方、あるいは企業の在り方の土台となるもの。パソコンに例えれば、OS(オペレーティングシステム)のようなものです。サービスやスキル、知識といったものは、そのOSの上で機能するソフトウェアです。
「ホスピタリティとは、おもてなしの心ですね」と言われる方もよくいますが、接客接遇のもてなしと捉えると、これはOSではなくなってしまいます。「もてなす」とは本来、「何をもって何をなすか」ということ。企業でいえば、何をもって何をなすためにこの会社があるのかを考えることが、「もてなす」ということです。
しかし、こうしたことを言い始めたのが早すぎたものですから、当初は誰も耳を傾けてくれませんでした(笑)。それでもリッツ・カールトンはこの考えを貫き、「ホスピタリティとは一人ひとりの生き方、働き方のOSである」とする姿勢を徹底してきました。そのことが、今のリッツ・カールトンをつくり上げ、結果として他社との差別化につながったということなのです。
また、先ほどのお話で言うと、私がいただく講演や研修のご依頼は、医療業界からのものが一番多いですね。次に多いのが自治体で、その次に流通業界や通信業界。製造業界からのご相談も多くいただきます。例えば自動車の部品メーカーであれば、完成車メーカーに納めることだけを考えるのではなく、その車に乗るファミリーの笑顔を想像できなければ、良い部品をつくることはできない。自分たちの製品を誰が使うのか、最終的な「シーン」を想像し、洞察することが必要だと。皆さんの考えが、急激にそちらに移行しているように思いますね。
時流に惑わされない、本質を見据えた取り組みを
────もはや、そうした本質に立ち戻るしか道はないということに、多くの企業が気づいているように思いますね。

本来、日本の商売はそういうものでしたよね。「三方よし」とよく言いますが、昔の商売人は「売り手・買い手・世間」の三方だけでなく、「天」も意識していました。「天に恥じない」という思いを常に持っていた。だから、本当は「四方よし」なのです。この思いが、日本の強さを支えてきました。その歯車がどこかで少し狂っただけのことですから、ホスピタリティに立ち戻るというのは、実は原点回帰なんですよ。
────ホスピタリティをそのように捉えている企業は、少ないように思います。
「ホスピタリティというものが話題になっているらしい」といったことで関心を持たれる企業もありますね。しかし、そうした姿勢では、せっかく研修を企画して社員の方々が真剣にディスカッションしても、何カ月後かに社長が「最近はこれが流行らしい」と別なことに目を向けたら、皆さんの意識もそちらに向いてしまいますよね。
────そういった企業では、受講者が高い意識でアウトプットしたものも、結局は取り上げられずに終わりますから、研修の成果が活かされません。すると経営者は「教育では会社は変わらない」と、教育そのもののせいにする。そして「何か別な方法はないのか」と。そんなことを繰り返す企業が、僕らの経験でも非常に多いなと思います。
ホスピタリティはOSですので、これを本気で会社の軸にするのは大変なことです。生き方そのものを変えなければいけないということが、たくさん出てきます。それでも取り組むのか、トップの覚悟が問われます。
しかし、なかにはトップが研修に参加されないこともあって、やむをえない事情なら仕方ありませんが、「ゴルフが入ったので」などとおっしゃると、私は何回かのシリーズの研修であっても、2回目以降はお受けしないこともあります。会社として何を目指すのかというトップの意思が、研修の参加者に伝われなければ意味がありませんから。
トップの夢とビジョンがない企業に、ホスピタリティは生まれない
────人財育成にも明確な考えがなく、何か曖昧模糊としたところで研修を実施されている企業も多いですね。
入社後のオリエンテーションや新入社員研修、その後の教育プログラムなど、教育体系を整えておられても、それぞれの位置づけが明確でないと、受ける側が今は何の時間なのかがわかなくなります。自分のどの筋肉を鍛えればいいのかと。ですから比較的わかりやすい、スキルや知識といった目に見えるものを教える研修が中心になってしまうのですね。
────私もまったくそう思います。結局、企業が見ているのは作業遂行能力なんです。我々はいろいろな企業で、社員の方々のアセスメントをすることがよくあります。管理職への登用時などに、外部の目も導入して能力を測ろうということでご依頼いただくのですが、そのときに僕は人事の方にこう申し上げるんです。「組織の長に一番大切なのは、"人に対する感性"と"組織に対する感性"です」と。この能力のない人が組織の長になると、管理するだけになってしまう。組織というのはそうして停滞し、活性化しなくなっていくのですと。
もちろん、スキルを教える研修や教育も大切ですが、リッツ・カールトンでは入社後の初期段階でそれらに使うエネルギーは、全体を100とすると25%ずつ。残りの50%は、夢とビジョンを共有することに費やします。具体的には、入社後のオリエンテーションで2日間をかけて夢とビジョンを語り、その後52週間にわたって心の筋トレを重ねるのです。
────つまり、企業に夢やビジョンがなければ始まらないということですね。
そうです。それがなければ、現場の社員のモチベーションも高まりませんよね。そして、仕事ではなく作業しかしなくなってしまいます。けれども夢を共有できると、自分が会社に存在する理由が見えるようになり、夢の実現に自分はどう役に立てるのかを考え始めます。教育で一番大切なことは、人間力を育てることです。人としての器を広げていく。それが心の筋トレにつながり、ホスピタリティマインドを持った人財を育むのです。
トップの言葉が社員の心を動かした、ある企業のケース
────リッツ・カールトンの「クレド」は有名ですが、従業員の方々は「クレド」をどのように受け止めておられるのでしょうか。
クレドカードには、ホスピタリティをOSにするための生き方がすべて書かれています。ですから、カードを見れば自分がそれに則っているかを確認でき、ふと迷ったときに見直すとブレを調整できる。不思議なことに、持っていることで安心感も生まれます。感性の「羅針盤」であり、働くうえでの「お守り」のようなものでもあるといえますね。

────クレドカードに類するものをつくって社員に配る企業もありますが、そのようにして働き方のスタンダードとして活用されているケースは非常に少ないように思います。リッツ・カールトンでクレドカードがそこまで浸透しているのは、やはりトップの本気度が違うということなのでしょうか。
トップの本気度を、どれだけあのカードに封じ込めるかということだと思いますね。クレドカードは、つくろうとすると上手くいかないんです。お客さまにどのような価値を提供する会社でありたいのか、社員にとってどんな会社でありたいのか。リッツ・カールトンでは、創業メンバーが何日もこうしたディスカッションを重ね、分厚いレポートにまとめたものを、海水を煮詰めるように言葉を削っていきました。そうして生まれた結晶が、クレドカードなのです。頭でつくったものは頭にしか伝わりませんが、心の中から生まれたものは相手の心に届く。この違いだと思います。
────まったくそうですね。とてもよくわかります。
一度だけ、ある企業のクレドづくりをお手伝いしたことがあります。今もそのクレドカードが機能している数少ないケースですが、「若い社員を集めてクレド制作委員会を立ち上げた」と社長がおっしゃるので、僕は「社長も参加してください」とお願いしたんです。
そして、会社の研修所で1泊2日のディスカッションを行い、初日は社長のビジョンや事業への思いを語っていただく時間にあてました。最初は「私の話なんて」とあまり言葉が出なかったのですが、昼頃から徐々にエンジンがかかってきましてね。学生時代のご経験から、それが今の経営にどうつながり、何を実現したいと思っておられるのかを、一気に話されたのです。
その間、委員会のメンバーには発言を控えてもらいましたが、初日の夕食時に「ここからは、皆さんの感想や意見を聞かせてください」と水を向けると、全員が一斉に話し始めました。「社長の話を初めて聞いた」、「もっと早く聞きたかった」と。
これでもう大丈夫だと思い、翌朝、社長には予定を切り上げて会社に戻っていただいて、委員会メンバーとディスカッションを始めたら、議論が止まらないんですね。一緒に働く仲間と何を共有したいか。5年後、10年後に、どんな会社であってほしいか。たくさん出た言葉をみんなで煮詰め、2日目が終わる頃には、粗削りながらも四つ折りのカードに言葉がびっしり詰まったクレドカードができあがりました。その後、その会社では時間をかけてさらに言葉を削り、今はかなりきちんとしたクレドカードができて社内に浸透しています。
────社長の思いが委員会メンバーの方々に伝わって、みなさんの心を動かしたのですね。合宿には参加していない社員の方々には、その思いどのようにして伝えていかれたのですか。
委員会のメンバーが、社長の思いを語るんです。
────みなさんが伝道師になっていかれる。
そうです。同時に、全社会議などの社員が集まる機会が増えるようになりました。社長がご自分の言葉のパワーに気づかれたのですね。社員は自分の話に興味を持たないと思っておられたのが、合宿で委員会メンバーが丸一日、目を輝かせて話を聞いてくれた。そこで社長の心にスイッチが入ったんです。ですから、クレドをつくったことで社長が一番変わられましたね。それは横で見ていてもわかりました。2日目の朝、会社に戻るときに、とても名残惜しそうにされていましたから(笑)。
────トップの心にスイッチが入って初めてホスピタリティがOSになり、そこからクレドが生まれ、機能していくということですね。
それが一番正しい形だと、僕は思います。
────人の変化や成長は、高野さんはどのようなところでお感じになるのですか。
目を見ればわかります。顔の筋肉はトレーニングできますが、目だけは鍛えることができませんから。本気の目をしている社長とそうでない社長って、おわかりになりますよね?
────ええ、わかります。
任期が3年、5年と決まっていてそのスパンで見ている方と、もっとずっと先を見据えている方とでは、目の輝きがまったく違います。私が尊敬するある経営者の方は、もう80歳近いお年ですが、100年先を見ておられる。覚悟の度合いが違うのです。クレドづくりをお手伝いしたその社長も、合宿の初日と2日目とでは目の輝きがまったく違いました。人は一日で変われるということなんですね。
ブレない組織の中心にあるものとは
────リッツ・カールトンでは、ホスピタリティがスタッフの方々に共有されているだけでなく、組織能力にまで高まっているように思います。組織全体にそこまで浸透させるにはどのようなことが大事になるのでしょうか。
やはり、トップの思いの強さですね。ホスピタリティを自分たちのOSにしてこの会社をつくるのだという覚悟が、トップにあるかどうかということです。うまくいかないケースは大抵、トップがブレています。リッツ・カールトンの創業者であるホルスト・シュルツィ氏は、彼が部屋に入ってきた瞬間にその部屋の温度が上がる気がするほど、太陽のように強烈な思いを持っていました。だから周囲に伝わるのです。
もう一つ、トップの思いを受け継ぐ2番手がいることも大切です。組織がなぜうまく機能しないかというと、これは私の個人的な理論ですが、地球は丸いのに、会社ができたときに三角形のヒエラルキー型の組織をつくってしまった。このあたりからおかしくなったのではないかというのが、僕の持論です。
丸型の組織では中心に太陽がいて、その思いに引き寄せられた二番手が衛星のように太陽を囲み、その周りに三番手がいるといった形で広がっていきます。実はリッツ・カールトンの組織は、このイメージに近いんです。もちろん役職はありますが、それはヒエラルキー型の組織のように権限の上下関係を表すものではなく、任されている役割が違うというだけのこと。そうした中で二番手が太陽の思いをしっかり受け継いでいれば、組織はブレません。これは非常に大切なことです。
ホスピタリティを企業の軸に据えるために必要なのは、トップの熱意と覚悟。そして、人財の採用と教育も非常に大切であると高野さんは語ります。ホスピタリティを持ち合わせている人財をどのようにして見極め、育てるのか。後編でご紹介します。
*続きは後編でどうぞ。
成熟化社会は、ホスピタリティが鍵となる(後編)
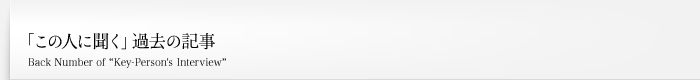
- 株式会社JR東日本テクノハートTESSEI
専務取締役 矢部 輝夫さん - 経営改革は、実行する「現場の実態」を把握して、初めて実現する(前編) - 千葉夷隅ゴルフクラブ
総支配人 岡本 豊さん - 企業の競争優位性は結果指標ではなく
それを生み出す組織の強さ、社員のモチベーションに規定される(後編) - 千葉夷隅ゴルフクラブ
総支配人 岡本 豊さん - 企業の競争優位性は結果指標ではなく、
それを生み出す組織の強さ、社員のモチベーションに規定される(前編) - 七福醸造株式会社
代表取締役会長 犬塚 敦統さん - 【事業で差別化しうるのは唯一人財のみ】
人が気づき、変わる瞬間とは(後編) - 七福醸造株式会社
代表取締役会長 犬塚 敦統さん - 【事業で差別化しうるのは唯一人財のみ】
人が気づき、変わる瞬間とは(前編) - 株式会社キングジム
代表取締役社長 宮本 彰さん - 【事業で差別化しうるのは唯一人財のみ】
知というアイデアを製品化し、利益に結びつける組織とは(後編) - 株式会社キングジム
代表取締役社長 宮本 彰さん - 【事業で差別化しうるのは唯一人財のみ】
知というアイデアを製品化し、利益に結びつける組織とは(前編) - 東海バネ工業株式会社
代表取締役社長 渡辺 良機さん - 【事業で差別化しうるのは唯一人財のみ】
やること、やらないことを決める
競争優位を明確にすることは、社員育成にもつながる(後編) - 東海バネ工業株式会社
代表取締役社長 渡辺 良機さん - 【事業で差別化しうるのは唯一人財のみ】
やること、やらないことを決める
競争優位を明確にすることは、社員育成にもつながる(前編) - 人とホスピタリティ研究所所長
前リッツ・カールトン日本支社長
高野 登さん - 【事業で差別化しうるのは唯一人財のみ】
成熟化社会は、ホスピタリティが鍵となる(後編)