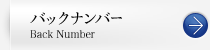OBT 人財マガジン

2008.04.23 : VOL44 UPDATED
-

学習院大学経済学部
教授 内野 崇先生
変化の時代を生き抜く「ヒトと組織の変革」とは(前編)
組織の改編やリストラ、人事制度の改革など、さまざまな企業においてさまざまな手法で変革が試みられています。しかし、それらの変革が成功する確率は必ずしも高いとはいえません。変革がうまくいかないとすれば、それはなぜか。何が変革成功の原動力になるのか。研究と実務の両面から企業変革に携わってこられた、学習院大学経済学部教授 内野 崇先生に伺ったインタビューを3回シリーズでご紹介します。
-
TAKASHI UCHINO

1951年生まれ。東京大学大学院博士課程を経て学習院大学教授に就任。主たる専門は経営組織論。組織学会理事。研究・教育に携わるかたわら、10数年にわたりエネルギー関連、商社、薬品、電器、IT、金融等の大手および中小企業を対象に、特にCI、戦略、組織改革、人事制度、給与制度等を中心にコンサルティング業務に従事。92年から96年にかけては学校法人学習院企画部長として21世紀計画の策定および、改革本部長として実際の学校改革にも従事する。著書に「変革のマネジメント(生産性出版刊)」、主要論文は「企業文化とその改革」「組織革新の動向」ほか多数。
-
「信じるに足る未来像」を掲げることが、変革成功の礎になる
────変革を目指す企業は数多くある一方で、成功例は少ないのが現状です。企業のこの状況をどうご覧になりますか。
変革が成功しない原因の一つはその出発点、「変革のトリガー(引き金)」にあります。例えば「トリガー」になりやすいものとして、「業績の悪化」がありますね。業績が下がってきたといって、慌てて変革に取り組む。しかし業績は遅行変数ですから、数字に表れたときにはすでに手遅れなんです。
また、各部門に現状を分析させて、出てきた課題の解決策を考えるというのもよくあるパターン。実はこれも問題で、このやり方では自分たちの部門で対処できる課題しかあがってこないことが多いのです。QCサークルなどならそれでもいいのですが、全社的な変革に取り組むときに現状分析からスタートするのは、あまり良いスキーム(枠組み)とは言えません。
では何が大事か。私はいつも「未来像」という表現を使うのですが、会社がどんな未来像を持っているのかということが、変革成功の鍵を握っていると思うんですね。そう考えるポイントは2つあるのですが、1つは未来像がなければ大胆な意思決定ができず、判断が前例踏襲主義になってしまうということ。
ベンチャーの草分けともいうべきある経営者が言っていた次の言葉も、まさにこれを象徴しています。「私たちは相場師ではないから、数カ月後の株価がどうなるかは分からない。しかし、3年後、5年後にどんな時代が来るのか、その時代の中で自社の位置づけがどうあるべきかということは、いつも考えています」と。未来像というのは、取捨選択の基準になりえる。今の時代には、そういう意識の強い経営者が必要です。
※内野氏の著書「変革のマネジメント(生産性出版刊)」では、会社の未来像に即した経営判断の例として、東芝の大型投資が紹介されている。以下、本書より抜粋(注釈はOBT人財マガジン編集部)。
「かつて東芝の大胆な投資が、ビジネスの世界で話題になったことがあります。1つは、世界における原子力発電の代名詞ともいうべきWH(ウエスチング・ハウス)の大型買収(*1)、もう1つは、半導体への積極投資です(*2)。両方併せると一兆円近い大型投資であり(中略)、会社としての「明確な未来像のデザイン」抜きには、こうした決断はありえなかったでしょう」。
*1 2006年に54億ドルで買収。
*2 2004年から2006年の3年間で半導体関連設備に5000億円近い投資を行った。もう1つのポイントは、未来像は従業員にとっての羅針盤にもなるということです。現実がどんなに辛くても、信じるに足る未来があれば人は生きていけます。その意味でも、会社が未来像を掲げることは非常に大事なんですね。
ところがこういう話をすると、「当社も中期経営計画は作っています」と言われる経営者が多い。しかし、未来像はそれとは少しニュアンスが違うんです。中期経営計画は、各部門が出してきた数字を取りまとめたものが多いですね。つまり、過去の延長型になる傾向があります。そうではなくて、未来像とは、例えば5、6年先にどんな会社にするかといった、もう少し踏み込んだ会社の未来の姿のことなんです。
そういった、中期経営計画よりももっと大きな未来像を掲げると、当然ながら現実との間にギャップが生まれることになりますが、そのギャップを埋めることこそが「変革」なのです。「現状分析」も、「業績悪化」も、変革のトリガーにはなりえない。「信じるに足る未来像を掲げ、現実とのギャップを埋める」。これが、変革の最大のキーワードです。
真の未来像は、過去の延長線上にはない
────中期経営計画は過去の延長になりがちだということですが、どのようにすれば過去の延長型の思考を脱却できるのでしょうか。

経験則で考えず、理論的に考えること。これがポイントです。例えば、自著で紹介した東芝のケースでいえば、西田厚聡社長は「これかはら原子力発電が有望だ」と考えたから大きな投資の決断をしたわけです。アメリカが原子力政策を転換し(*3)、原油も値上がりしてきている。中国もこれから原子力発電所をたくさん作ることになるだろう、と。
*3 2001年5月にブッシュ大統領が「国家エネルギー政策」を発表。温室効果ガスを排出しない原子力エネルギーの利用拡大を支持した。
ところが当時はヨーロッパで脱原子力政策がいわれていたことから、マーケットには「原子力発電はそれほど伸びない」という見方もあった。実際どうなったかといえば、全世界的な原子力発電の見直しがあり、東芝は見事にその時流に乗りました。
一方で、未来像の構想に失敗した例もあります。例えば、今、新東京銀行の経営悪化が問題になっていますね。「中小企業を支援する」という未来像を掲げていたわけですが、実は企業に対するお金の入れ方には融資以外にもう一つ方法があります。株式を発行させて、その株式を買う。つまりファンドを設立して投資するという方法です。
ファンドは当たれば100倍になることもありますから、20社に投資して1社当たれば成り立つけれども、融資は利回りがせいぜい7%程度。20社に融資して19社が倒産したら、もうどうしようもない。つまり、ハイリスク・ハイリターンの世界で戦わなくてはいけなかったのに、ハイリスク・ローリターンの世界で勝負してしまったわけです。
こういったことは、あらゆる企業についていえるのではないでしょうか。未来を構想するには徹底して理論的に考えて、あらゆる可能性を検討することが必要です。理論的に考える力と未来を構想する力はセットなんですね。
もう1つ必要なのは、未来像という「今はまだないもの」を信じる力です。逆にいえば、「あるもの」を疑う力。過去と現実は目の前にありますが、それを信じると危ない。「ないもの」を信じる力こそが大切なのです。
────経営者にとってみれば、とても勇気のいることですね。
ええ、勇気がいりますね。リスクを取るような変革をするよりも、過去の経験則に従ったほうが安全ですが、実は勇気のいることこそがビジネスの本質。その認識を持たない経営者の方も意外に多いのではないでしょうか。
変革成功の鍵を握るのは、現場のリーダーの力
────では、企業の未来像を描くのは、やはり経営者の役割なのでしょうか。
いえ、むしろ各部門がそれぞれに未来像を描くことが大切です。トップは現実のさまざまなビジネスに精通しているわけではありませんからね。ですから、ある種の知的格闘技といいますか、自分たちの会社の未来について、若い人も含めてもっと自由に意見が出るような仕組みを作るべきだと私は思いますね。会社全体を未来志向にするということです。
ところが最近はリスクマネジメントが強すぎて、失敗に対して大きなペナルティを課す会社が多い。アイデアは会社の中にたくさんあるのに、経営者が握り潰しているケースもあります。そんな中で「未来志向」といっても、それではかけ声倒れ。変革に成功する組織になるためには、この状況をどのように再生するかということが非常に大切になります。
────どうすれば、会社を未来志向にできるのでしょうか。
キーワードは、「ミドルマネジメント」です。「社長がすべてを決めて、現場はそれを実行するだけ」とならないことが大事なのであって、そのためには「経営者と部門長の連携」や「部門長のマネジメントスタイル」が重要になるんですね。
────しかし多くの企業で、現場は業務に忙殺されています。未来像を考える余裕がないミドルマネジャーも多いのではないでしょうか。
多いでしょうね。昨年の10月に、当大学の学生約200人を対象にあるアンケートを実施したのですが、そこでも同様の結果が出ました。「あなたのお父さんは、幸せそうに仕事をしていますか」と聞いたんです。そうしたら、200人中105人の学生が「幸せそうには見えない」と言う。「なぜか」と聞くと、「いつも疲れている」「家族に気を使って元気そうに振舞っているが、やはり辛そうだ」と。これは異常な事態。非常にショックを受けました。
もう1つ、現場の疲弊を象徴する寓話があります。「金の卵とガチョウ」という、イソップ童話がありますね。あの話の最後では、欲深い農夫が金の卵欲しさにガチョウの腹を裂いて殺してしまいますが、実は、会社もそれと同じことをしているわけです。金の卵ばかりを見て、ガチョウの体力が落ちていることに気づいていない。実際、多くの職場はガタガタになっています。
現場を取りまとめる部長や部門長はどうかといえば、叩き上げで管理職になっていますからマネジメントが自己流になってしまっている。しかも部門長の評価は、たいていは業績評価のみ。実はこれが一番問題で、態度やプロセスの評価は一切なく、要するに結果が大事だということなんですね。ですからマネジメントがマネジメントの体をなしておらず、かなりひどい状況の部門もあります。
そういった部門の部下の人たちに「辛くないか?」と聞いたら、「辛いけれど、どうしようもありません。いずれ今の部門長は去りますから、それまでの我慢です」と言うんですね。これはまさにリーダーシップの劣化そのものです。
ガチョウの体力が落ちていては、金の卵を産むことはできません。変革リーダーというと「戦略を実現して、何か新しいことをする人」というイメージを抱きがちですが、まずはその定義を変える必要があるのではないでしょうか。
本当の変革リーダーとは、「職場を元気にして、職場とヒトの劣化を防ぐ人」。つまり、ガチョウの体力をどう強化するか。劣化した職場を再生できるミドルマネジャーを輩出することに、経営者はもっと一生懸命になるべきなのです。
日本の多くの企業現場で、目に見えない職場の制度疲労の蓄積が進行していると、内野先生は警鐘を鳴らします。では、職場とヒトの劣化は、なぜ進んでしまったのか。中編では、企業社会が抱える問題の構造について伺います。
*続きは中編でどうぞ。
変化の時代を生き抜く「ヒトと組織の変革」とは(中編)
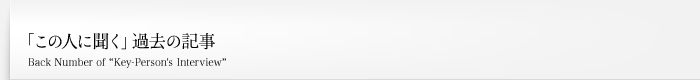
- 株式会社JR東日本テクノハートTESSEI
専務取締役 矢部 輝夫さん - 【事業で差別化しうるのは唯一人財のみ】
企業改革を阻む制約をいかに克服するか(前編) - 千葉夷隅ゴルフクラブ
総支配人 岡本 豊さん - 【事業で差別化しうるのは唯一人財のみ】
見えざる資産を競争優位にするために必要なこと(後編) - 千葉夷隅ゴルフクラブ
総支配人 岡本 豊さん - 【事業で差別化しうるのは唯一人財のみ】
見えざる資産を競争優位にするために必要なこと(前編) - 七福醸造株式会社
代表取締役会長 犬塚 敦統さん - 【事業で差別化しうるのは唯一人財のみ】
人が気づき、変わる瞬間とは(後編) - 七福醸造株式会社
代表取締役会長 犬塚 敦統さん - 【事業で差別化しうるのは唯一人財のみ】
人が気づき、変わる瞬間とは(前編) - 株式会社キングジム
代表取締役社長 宮本 彰さん - 【事業で差別化しうるのは唯一人財のみ】
知というアイデアを製品化し、利益に結びつける組織とは(後編) - 株式会社キングジム
代表取締役社長 宮本 彰さん - 【事業で差別化しうるのは唯一人財のみ】
知というアイデアを製品化し、利益に結びつける組織とは(前編) - 東海バネ工業株式会社
代表取締役社長 渡辺 良機さん - 【事業で差別化しうるのは唯一人財のみ】
やること、やらないことを決める
競争優位を明確にすることは、社員育成にもつながる(後編) - 東海バネ工業株式会社
代表取締役社長 渡辺 良機さん - 【事業で差別化しうるのは唯一人財のみ】
やること、やらないことを決める
競争優位を明確にすることは、社員育成にもつながる(前編) - 人とホスピタリティ研究所所長
前リッツ・カールトン日本支社長
高野 登さん - 【事業で差別化しうるのは唯一人財のみ】
成熟化社会は、ホスピタリティが鍵となる(後編)