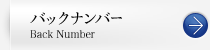OBT 人財マガジン

2008.07.09 : VOL49 UPDATED
-

青梅慶友病院
理事長 大塚 宣夫さん
「理想の病院作り」に学ぶ、理念型組織のあり方(前編)
企業経営における理念とは、企業が存在する理由そのもの。短期的な業績ばかりが重視される風潮が広がり、利益至上主義による企業の不祥事が後を絶たない今の時代、企業理念のあり方が、改めて見直されています。どうずれば理念は組織に浸透するのか。どうすれば理念を風化させず、創業の志を保ち続けられるのか。「親を安心して預けられる病院」という理念を掲げ、老人病院にサービス業の発想を持ち込んだ医療界の異端児、青梅慶友病院・理事長、大塚宣夫さんに伺ったインタビューを2回シリーズでご紹介します。
-
青梅慶友病院 (http://www.keiyu-hp.or.jp/oume/index.php)
1980年2月開院。いち精神科医であった大塚宣夫氏が、「親を安心して預けられる病院」という理念を掲げ、土地探しから奔走して病床数147床で起業。その後3度の増築を経て、病床数736床の大病院に。「医療はサービス業である」という強い信念のもと、職員の360度評価、入院患者の「寝たきり起こし」など、業界の常識を覆す施策を次々と導入する。2005年には「よみうりランド慶友病院」を遊園地「よみうりランド」の敷地内に開院。遊園地と老人病院という異色の組み合わせが、業界内外の話題を呼んだ。
NOBUO OTSUKA
1942年生まれ。医学博士。1966年に慶應義塾大学医学部卒業。67年に同大学医学部精神神経科学教室入室。井之頭病院勤務、フランス政府給費留学生としての2年間のフランス留学を経て、80年に青梅慶友病院を開院し院長に就任。88年には同病院を医療法人社団慶成会に改組、理事長に就任。2005年によみうりランド慶友病院を開院。著書に「老後・昨日、今日、明日」(主婦の友社刊)、監修書に「百歳回想法(ソトコトclassics)」(木楽舎刊)。
-
「こんなはずでは...」。アクシデントの連続を乗り越えた創業期
────病院の開設から28年目を迎えられました。今や業界の内外から注目される存在でいらっしゃいますが、どのようなステップを経て今日を築かれたのか、まずは開業当時のことからお伺いさせてください。
自分の親を安心して預けられる病院を作りたい。ただその思いだけで起業したものですから、組織の運営などしたことがなく、一勤務医としての経験しかない中で病院を立ち上げました。思いのたけはありましたが、何をどうするという深い考えがあったわけではなく、まさに手探り。最初の5年間ぐらいは本当に「創業期」という感じでしたね。
お陰様で資金繰りの苦労はありませんでしたが(※)、大変だったのは人集めです。当時はまだ老人病院のイメージが悪く、そんな所で働こうという人はよほどの変わり者か何かの事情で働く場所がなくて困っている人ばかり。こちらが経営の素人なら、スタッフは言ってみればはみ出し者の集まりだったわけです(笑)。
※編集部注:資金繰りは、大塚宣夫氏が開業準備に奔走する中で出会った、霞農業協同組合(現・西東京農農業協同組合)の組合長(当時)、野崎省吾氏が全面的に支援した。大塚氏の熱意に動かされた野崎氏は、自身の所有する約1000坪の土地を貸与し、運転資金借り入れのための連帯保証も引き受けたという。
────医療業界の中で、老人病院がどう見られていたかはご承知の上でお始めになったのですか。
あまり深くは考えていませんでしたね。ですから、開業準備中に「そんなにしてまで金儲けがしたいか」と周囲に言われたときは、衝撃的でした(笑)。
────それは、ひどいですね。
老人病院といえば、その程度の見られ方ですよ。行き場のないお年寄りをベッドに縛りつけて、検査漬け、点滴漬け、薬漬け。それで稼ぐといったイメージで、悪徳病院の代表のようなものでしたから。
────そういった中で、大塚先生が描かれた病院の理想像はどのようなものだったのでしょうか。
具体的に「これ」という事があったわけではないんですね。良心的な医療を提供すれば、お年寄りは元気になるのではないかという程度の考えだったわけです。しかし現実には、医療行為をどれほど良心的に行っても元気にならない。やればやるほど、世に言われる老人病院の姿に近くなっていく事を思い知らされたんです。「こんなはずではない」という毎日でしたね。
────やめようと思われた事はありませんでしたか。
始めた以上は荷物を背負ったわけですから後戻りはできませんが、「こんなことなら、やるんじゃなかった」と思う毎日でしたね(笑)。職員が集まらない中で病院を運営することが、こんなに大変なこととは思いませんでした。
病院を始めた当初は資金が限られているものですから、最低限の人数で始めたんですね。看護師10人でスタートしたのですが、開業して3カ月ほど経ち、入院者も60人くらいになった時点でそのうちの6人が一斉に辞めてしまったんですよ。「仕事があまりにも凄まじい」と言うんですね。老人病院ですからお年寄りには手がかかるし、開業したてで仕事の流れも定まっていない。婦長として私の片腕になってくれていた人が「もう私には務まりません」と言い出したら、他の5人が「辞めます」と言って6人がどっと退職してしまったんです。
翌日からは、残った4人の看護師で60人を超える患者様を看る毎日です。その日の夜勤を頼める人をようやく見つけてお願いして、翌朝にその人が帰ると、院内に残っているのはその日が初出勤の看護師とパートの人だけというような状況。業務そのものが、とにかく回らないわけです。募集すると少しは応募がありましたが、みんなその凄まじさに驚いてね(笑)。一日で次々と辞めていって、それはもう大混乱でした。
────その時はどんなご心境でしたか。
ともかく、今夜をどうしのぐか、明日をどうしのぐかという事しかなかったですね。医師も実質的には私とパートの先生を順番につないで、ようやく回すという状況です。薬剤師もパートの人だけでしたし、レントゲンの技師に至ってはそもそもいない。医者はレントゲン撮影も調剤もできる資格がありますから、全部自分でやる。当直も頼むとお金がかかりますから、自分でやる。
2月にスタートして、その年は正規の当直だけで130回ほどやりました。その他に約100日病院に泊まりましたから、最初の年はほとんど家に帰らなかった。そういう時期があったお陰で、病院経営がいかに大変なものかが分かりましたね(笑)。
────職員の方々が定着するようになったのは、いつ頃のことですか。
9カ月ぐらい経ってからですね。特段何かをしたわけではないんですが、何人か核になる人に頼んで仲間を連れてきてもらうといったことで、徐々に定着するようになってきました。

今では、法定人員の1.5倍(常勤換算)の職員を配置。その分入院費は他の病院に比べて高額になり、4人部屋で日額約1万円、個室は2万円。入院費が高いことを指摘される事もあるというが、「この病院は、豊かな最晩年を開発するための実験研究センター」(大塚氏)と、理想を追う姿勢を崩さない。各病棟には担当スタッフの名前が顔写真入りで公開されている。
流れに逆らわず、逆境をチャンスに変える
────では、現在のこの病院の姿を理想と描いて始められたわけではなかったのですね。
そんな先まで考える余裕は、全くありませんでしたね。今日一日をどうしのぐかという、とにかくそれだけでしたから。うちのいろいろな取り組みというのは、外部的な要因で転がってきた物が多いんです。過剰な医療をしないという方針もそう。開業して7、8カ月ほど経った時でしたか、健康保険組合に保険請求をしたらバッサリと拒否されてしまったんです。他の悪徳病院と同じに見られたんですね。それなら点滴も薬も全部やめてやろうというくらいの対応をしたら、お年寄りたちがずっと元気になってきたんですよ。
点滴や薬よりも、むしろ職員の手による介護の方がずっと元気になると知って、「目指すものはこれだ」と。そこで方向転換をしたんです。ここからですね、うちのスタイルができてきたのは。
────保険請求を拒否されたことが、思わぬきっかけになったのですね。
そう。それがあって一大転機を迎えたんです。
────同時期の1982年には、体育大学の出身者を「生活活性化員」として採用するといったことも始めておられます。
これも、外部的な要因から始まったものです。当時はリハビリの職員を募集しても、応募がまったくなかったんですよ。リハビリの勉強をしている人たちは、老人病院で働くなんて思ってもみないんですね。それなら、元気のいいのをどこかから探してくればいいという程度の発想です(笑)。
私の家内の母が体育大学で教えていたものですから、「大学で就職に困っている人はいないか」と声をかけてみたところ、たまたま来たのがとてもいい男でしてね。そうだ、こういうイメージの人を院内にたくさん配置すればいいんだということで、その翌年から何人かまとまって採用するようになったんです。
────体育大学からは、学生の応募はありましたか。
応募と言うよりは、体育大学を出たけれども教員採用試験に受からず、次の試験までやる事がないといった人たちが、まず第一候補。1年のつなぎでもいいから、元気のいいのを送ってくれという話で事がスタートしたわけです。
リハビリの職員の仕事は患者様を元気にすること。それなら資格を持っていなくても、ともかく元気のいい人に来てもらおうと。そうしたら他の職員も元気が出るんじゃないか、みたいなね(笑)。
────採用された方は戸惑われたのではないですか。
そりゃあ、何をしていいか分からない中に、突然放り込まれたわけですからね(笑)。私が伝えたのは、「あなたの役割は、この病院の中を少しでも活気づけることだ」と。これだけです。第1号として来てくれた男が大変なアイデアマンで、自分で道を切り開ける人材でしたので、それは本当にラッキーだった思いますね。彼は結局、うちの病院に10年以上いて、生活活性化員の位置づけや患者様向けのレクリエーションといったものを、みんな自分で切り開いて作ってくれましたのでね。今では出身母校である仙台大学に准教授として迎えられて、福祉レクリエーションの第一人者として活躍していますよ。


15ある病棟それぞれに生活活性化委員が配属され、日曜日を除いて毎日、生活活性化員や理学療法士による「体操・筋力強化トレーニング」が実施されている(写真左)。また、入院患者の豊かな生活を実現する専門職として、生活活性化委員の他にレクリエーションワーカーを配置。病棟ごとの患者の健康状態に合わせて、「ビデオ鑑賞会」や「趣味の会」などを企画している(写真右)。
常識を疑う。そこから新たな道が開ける
────開業4年目の1985年には、患者様の身体抑制(手や体をベッドに縛ること)を廃止されました。これも、老人医療に一石を投じるためのお取組みだったのでしょうか。

いや、そんなに大それた考えではなくて、これもたまたまだったんですよ。その頃にはうちも老人病院の世界で少しずつ知られるようになっていまして、ある時、週刊朝日の大熊一夫さんという医療問題を告発して歩くことで有名な記者が、うちの病院を「泊まり込みで一週間取材させてくれ」と言ってきたんです。
かつて私が精神科の勤務医だった時に、近くの病院がやはり彼に告発されて、半潰れ状態になったことがありましてね。「いよいよ、うちもこの人に潰されるのか」と(笑)。断ったらまた何を書かれるか分かりませんから、こうなったら病院の中のあらゆる物を見てもらおうと覚悟を決めたわけです。
そして彼が来た初日に、こう言いました。「あなたに書かれることでこの病院は潰れると、私も覚悟を決めた。ただ、どうせならあなたが来た記念に、今夜から患者様の抑制を全部止める。それでどんなことが起こるか、あなたもつぶさに見てよ」と。彼がうちの病院を見て一番興味を持つのは何かと考えたら、患者様の抑制だろうと思ったんです。
認知症が進んだ患者様というのは、夜になると不穏になって一斉に動き出すんですね。それを防ぐために、夜はベッドに縛りつけるという状況があったわけです。患者様を縛りつけるなんて人権侵害も甚だしいけれども、夜中に動いたら転んで骨折する危険もあります。それを防ぐためには縛らなくてはいけない。だから「あなたが最も書きたくなる事のはずだから、開き直って今夜から全部ほどくことにする」と。職員には「一切縛るな」と指令を出したんです。
そうして翌朝に様子を聞いてみたら、看護師たちが「皆様、とても静かでした」と言うんですよ。もう、「えーっ!」と驚きましてね。骨折防止だとか、他の患者様に危害が加わるのではないかと考えていたことは、みんな私たちの思い込み。夜中に大声を出していたのは、縛られる事を嫌がっていたからなのでしょうね。そこで以降は、「縛る事一切まかりならぬ」という運営に変えたわけです。ですから、そんなに高い志があってやったわけではなく、外部的な要因によって実現された事なんですね。
────抑制を止める事による、最悪の事態も想定されましたか。
その時は、その時です。そう考えるしかないですよね。
────事故は起こりませんでしたか。
まったく起こりませんでした。
────記者の方も驚かれたのではないですか。
そう、大熊さんもびっくりですよ(笑)。ですから結局、その時の週刊朝日の記事はまったくネガティブな感じではありませんでしたね。
────保険請求が拒否されたから点滴や薬を止めよう、週刊誌の記者が取材に来るから抑制を止めようといった決断は、どういったご心境でされるのですか。
もう、開き直りなんですね。自分が今までやってきた事が正しいのか、あるいはあなたの言うことが正しいのか、と。私はすぐに開き直ってしまうんですよ(笑)。
思い切った権限委譲で、現場の自主性を育てる
──── 一方で組織運営の面でも、病棟の独立運営制や委員会制度などユニークな取り組みをされています。どのような経緯でこれらの仕組みを作られたのでしょうか。
病棟の独立運営制は、増築がきっかけです。病床数147床でスタートして、2年後には283床になり、その3年後に2回目の増築をして558床になった。1985年の夏ごろのことです。283床の時には病棟が4つありまして、その4つの病棟のコントロールにはすごく苦労したんですね。
当初は、どの病棟も同じクオリティで運営される事がいいと思って、いろいろな事をマニュアル化し、中央の指令のもとに運営していました。だけども、みんなで「こうしよう」と決めたことも、翌日から各病棟でまったく違った風にやっている。なぜかというと、各病棟にはそれぞれの事情があるんですね。構造的な問題や患者様の状態が違うから、同じように動かすことは難しいわけです。
そんな中で2回目の規模拡大が決定し、病棟が4つでも大変なのに7つになったら、クオリティなんてどこかへすっ飛んでしまうのではないかと思いましてね。それならいっその事、7つの病院があると考えて、「各病棟が自由に運営してよい」という風に変えようと。「運営は各病棟の看護師長に一任する。各病棟のスペースとベッド数に応じた職員数と予算をあげるから、やりたいようにやってくれ」と、発想を変えた。それが、病棟独立運営制のスタートだったんです。
ですから、さらに上を目指してやったというよりは、これまた開き直りでね(笑)。今までのやり方ではもうダメだから、「あなた方に任せる」ということだったわけです。
────各病棟に任せる事は、怖くはありませんでしたか。
その気持ちは十分ありました。何が起きるか分かりませんのでね。だけども、ともかくやってみてダメならまた考えればいいという、その程度の発想ですよ。私は、物事をあまり深くは考えないんです。何事もやってみないと分かりませんからね。
────任せたものの、やはり口を出したくなるといった事はありませんでしたか。
そういうことは、なかったですね。私の手のかかり方は今までの半分以下になり、各病棟のクオリティは今までよりも上がった。スタートからとてもうまくいきました。
それまで中央で持っていた予算を各病棟に与えるようにしたら、例えば、何本支給してもすぐ足りなくなっていたボールペンや消しゴムといったものの消費が半分以下になったんですよ。家にあまっている鉛筆やボールペンを持ち寄ったりしてね。花なども、中央の予算で買っていた時には、提供してもすぐに枯らしてしまう。だけども、「自分たちの予算で買え」と言った途端に、枯らさないどころか「花屋から買うのはもったいない」と、みんな自分の家から持ってくるようになったんですよ。
────大変な変化ですね。
そういう事なんだと思うんですね。自分たちの裁量で物が買えるようになりましたから、そうやって予算を捻出して、自分たちが欲しい食器棚や家具調度類を買えるような状況にしていくんですね。
────病棟独立運営制の導入準備として、職員教育といった事もなさったのでしょうか。
もちろん、師長を集めて話はしょっちゅうしますね。彼女たちなりに、「これはどうすればいいのか」といった事がたくさんありますから。絶えず会議もしましたし、夜の飲み食いもしました。そういう意味では手がかかりましたが、生産性はずっと上がりました。
中央からの指令で「あれをやれ」「これをやれ」と言われていた時の方が、「どうすればいいか分からない」という事が多かったように思います。病棟独立運営制にしてからは、「患者様に一番喜んでもらえる事、あるいはご家族に喜ばれる事を考えろ」と。指令はそれだけですから、みんなそれぞれに考えて、いろいろやっていましたね。


病棟には、職員のアイデアから生まれたさまざまなイベントのお知らせが掲示されている。中でも1992年から続く「慶友コンサート」や1994年に始まった「美食倶楽部」(プロの料理人を招いての食事会。写真右)は人気のイベントだという。
現場に任せた分だけ、現場とのコミュニケーションを強化する
ところが、しばらくやっているうちに、病棟間のいろいろな格差が見えるようになってきたんですね。そこで、最低限のクオリティを保つための指標を決めて、品質評価をやるようにしようと考えて始めたのが委員会制度です。これも、「最低限これだけは達成してくれ」という、その程度の発想なんですよ。
────委員会はいくつ作られたのですか。
「品質評価委員会」と「サービス向上委員会」、もう1つは、当時は違う名前でしたが「フードサービス研究会」というものと、3つですね。
────委員会のメンバーはどのように選ばれるのですか。
うちでは、組織はできるだけフラットにいきたいと思っていますので、各病棟の責任者は師長1で、それ以下の役職者は一切置いていません。ただ、そうすると師長1人で30人から40人の職員を見ることになります。病院の方針を伝えるには1人だけでは弱いし、現場の意見を吸い上げるにも、やはり師長1人を通してだけでは弱い。そこで、委員会には師長をサポートする役割も持たせているんです。
ですから、各員会のメンバーは各病棟の中核になっているナンバー2、ナンバー3、ナンバー4といった人たち。病院からの情報はその人たちに対しても積極的に出し、その人たちを通して各病棟の情報を取るという仕組みです。
例えば、何か新しい施策を導入してみて、師長からは「とても上手くいっています」と報告が来ているけれども、他の委員会メンバーに聞くと「いや、大変です」と、言うことが違うとかね(笑)。それを聞いて少し方向を変えてみるといった事は、たくさんあります。師長を補佐するバイパスとして委員会メンバーがいることで、チャネルが非常に多くなったんですね。
職員の採用難や健康保険組合による保険請求の拒否など、予期せぬ偶然のアクシデントをチャンスに変えることで青梅慶友病院は発展を遂げました。しかし理念型組織の実現は、「偶然をチャンスに変える力」によるものだけではありません。どのようにして、組織に理念を浸透させたのか。後編では、評価や採用などの人事面の施策を伺います。
*続きは後編でどうぞ。
「理想の病院作り」に学ぶ、理念型組織のあり方(後編)
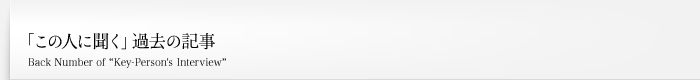
- 株式会社JR東日本テクノハートTESSEI
専務取締役 矢部 輝夫さん - 【事業で差別化しうるのは唯一人財のみ】
企業改革を阻む制約をいかに克服するか(前編) - 千葉夷隅ゴルフクラブ
総支配人 岡本 豊さん - 【事業で差別化しうるのは唯一人財のみ】
見えざる資産を競争優位にするために必要なこと(後編) - 千葉夷隅ゴルフクラブ
総支配人 岡本 豊さん - 【事業で差別化しうるのは唯一人財のみ】
見えざる資産を競争優位にするために必要なこと(前編) - 七福醸造株式会社
代表取締役会長 犬塚 敦統さん - 【事業で差別化しうるのは唯一人財のみ】
人が気づき、変わる瞬間とは(後編) - 七福醸造株式会社
代表取締役会長 犬塚 敦統さん - 【事業で差別化しうるのは唯一人財のみ】
人が気づき、変わる瞬間とは(前編) - 株式会社キングジム
代表取締役社長 宮本 彰さん - 【事業で差別化しうるのは唯一人財のみ】
知というアイデアを製品化し、利益に結びつける組織とは(後編) - 株式会社キングジム
代表取締役社長 宮本 彰さん - 【事業で差別化しうるのは唯一人財のみ】
知というアイデアを製品化し、利益に結びつける組織とは(前編) - 東海バネ工業株式会社
代表取締役社長 渡辺 良機さん - 【事業で差別化しうるのは唯一人財のみ】
やること、やらないことを決める
競争優位を明確にすることは、社員育成にもつながる(後編) - 東海バネ工業株式会社
代表取締役社長 渡辺 良機さん - 【事業で差別化しうるのは唯一人財のみ】
やること、やらないことを決める
競争優位を明確にすることは、社員育成にもつながる(前編) - 人とホスピタリティ研究所所長
前リッツ・カールトン日本支社長
高野 登さん - 【事業で差別化しうるのは唯一人財のみ】
成熟化社会は、ホスピタリティが鍵となる(後編)