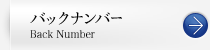OBT 人財マガジン

2011.06.08 : VOL117 UPDATED
-

日本理化学工業株式会社
取締役会長 大山 泰弘さん「人を仕事に」ではなく、
「仕事を人に」あわせて生産性を高める逆転の発想(前編)チョークの製造で国内トップシェアを誇る日本理化学工業では障害者雇用を推し進め、社員の7割以上が知的障害者だ。しかしながら同社はそれをハンディキャップとしていない。製造工程を工夫することで他社に劣らない生産性をあげ、社員の幸福と企業の成長を同時に実現している。「障害者の方々に支えられて今がある」「人のために一所懸命にやっていると多くの人が応援してくれる」大山会長はこれ迄の道のりをこう振り、「利他の経営」が企業存続の秘けつであると語る。社員があって為される仕事か、仕事のためにいる社員か―何を重視するかによって企業の在り方は大きく変わる。(聞き手:OBT協会 伊藤みづほ)。
-
[OBT協会の視点]
「幸せになりたかったら、まず、人を喜ばすことを勉強しなさい」──これはイギリスの詩人、M・プリオールの言葉です。自分の幸せしか考えられない人は、結局のところは幸せになれない。相手のことを第一に考えて行動すれば、結果は自分に返ってくる。人の幸せの道を「利他の精神」に見出すこの言葉は、企業経営にも当てはまるのではないでしょうか。真のリーダーに求められるのは、人に尽くす精神や、他人の幸せを自分の喜びに思える感性。この資質を持たない人がリーダーになると、組織の歯車が狂い始め、現場が疲弊し、不祥事といわれるような間違いが生じます。日本理化学工業の大山泰弘会長が貫かれているのも、まさに「利他の経営」。これを「きれいごと」と見るか、「真理」と受けとめるかによって、今後の自社のありようが見えるインタビューです。
-
日本理化学工業株式会社 ( http://www.rikagaku.co.jp/)
1937年設立。石膏チョークが主流で教師に肺結核が多かった日本で、初めて炭酸カルシウム製チョークの国産化に成功。衛生無害なチョークとしてシェアを伸ばす。1960年から知的障害者の雇用に取り組み、1975年に全国初の心身障害者多数雇用モデル工場を開設。1981年には北海道美唄市にも同モデル工場を開設。これが縁となり、北海道立工業試験場との共同研究によって世界的にも稀なホタテ貝殻を再利用したダストレス・チョークを、2005年に開発。同年、粉がまったく出ない固形マーカー「キットパス」を早稲田大学と共同開発。幼児教育などの分野にも販路を拡げる。長年に亘る障害者雇用が評価され、労働大臣賞や企業フィランソロピー大賞社会共生賞など受賞歴も多数。
企業データ/資本金:2000万円、従業員数/74名(2011年5月現在)YASUHIRO OHYAMA

1932年生まれ。父が設立した日本理化学工業に、1956年、大学卒業と同時に入社。病身の父の後を継ぎ、1974年に社長に就任。2008年から現職。1960年から障害者雇用に取り組み、障害者雇用割合70%を実現。その経営姿勢が評価され、2009年に渋沢栄一賞を受賞。 著書に「働く幸せ」(WAVE出版刊)、「利他のすすめ」(同)。
-
終業チャイムにも気づかず、夢中で働く。何が彼女たちをそうさせたのか
────御社は1959年から知的障害の方々の雇用を積極的に進めておられます。人を大切にすることと業績をあげることは両立しうるのか、今日は、障害者雇用に取り組んでおられるお立場からお感じのことをお聞きできればと思います。
1959年というと、昭和34年ですね。その年の秋に、東京都立青鳥(せいちょう)養護学校という学校の先生が、生徒さんの就職依頼に訪ねて来られましてね。まだ中等部までしかなく、15歳で卒業していた時代です。就職できなければ、親元を離れて施設に入らなくてはいけない。先生は何とか就職させたいと、思案したんですね。学校で使う品物の中で、チョークがいちばん簡単に作れそうだと(笑)。箱を見たら「日本理化学工業」と書いてあった。それで訪ねてこられたんです。
しかし、その頃はまだ「知的障害者」ではなく「精神薄弱児」と呼んでいましたから、「精神のおかしな人なんて、とんでもない」と、私は大変ひどい言葉でお断りしました。けれども、その先生は二度、三度と訪ねて来られた。「就職は無理でも、せめて一生に一回、『働く』ということを経験させてから、施設に送ってやりたい」と。「一生に一回」なんて言われたら、少しお手伝いしなくてはいけないかなと、2週間の実習を受け入れたことがきっかけです。その時に来た2人のうちの1人は66歳になりますが、まだここで働いてくれているんですよ。
────50年以上もいらっしゃるのですね。
そうです。実習にきた当時、彼女たちがとにかく一所懸命でしてね。昼のベルが鳴っても気がつかずに、「お弁当を食べるベルですよ」と声をかけるまで仕事をしているんです。その姿が、周りに何かを感じさせたんですね。まして15歳といえば、社員にとっては自分の娘のような年齢です。その子が親元を離れて施設に行くのは可哀想だという、同情心もあったのでしょう。「私たちが面倒をみますから、雇ってあげてください」とみんな言うものだから、「2人くらいなら、何とかなるかもしれないね」と。そこで翌年、1960年に2人を採用したことが始まりです。
企業は、人間に「究極の幸せ」を与えることができる

しかしその時は、まさか私が知的障害者の雇用に取り組むことになろうとは思いもしませんでしたが、その後、たまたま法事で訪れた禅寺でご住職とお話する機会がありましてね。どうして彼女たちはあんなに一所懸命に働くのかと、以前から疑問に思っていたことを、ふと質問してみたんです。すると、ご住職はこう言われました。「人間の究極の幸せは次の4つです。人に愛されること、人に褒められること、人の役に立つこと、人から必要とされること。褒められたり、役に立ったり、必要とされることは、施設では得られない。人間を幸せにできるのは、企業なんですよ」と。
企業が人を幸せにするなんて思ったこともありませんでしたから、この言葉には驚きました。それが人間の幸せなのであれば、一人でも多くの知的障害者が働ける場になるように頑張ろうと。それで、多数雇用を目指すようになったのです。
もう一つ後押しになったのは、国の施策です。昭和35年に「身体障害者雇用促進法」が制定されましたが、企業での雇用が進まず、昭和48年に障害者を多数雇用するモデル工場をつくるための融資制度を国が立ちあげました(※1)。これに応募しないかと、労働省(当時)から連絡をいただいたんです。昔、石田博英労働大臣(※2)が当社を視察されたことがあって、その記録が残っていたんですね。「身体障害者雇用の申請はあるが、知的障害者を雇用する会社がない。日本理化学さんが応募してくれませんか」と。
※1 心身障害者多数雇用事業所に対する特別融資制度
※2 1957年から1977年にかけて、4回、計4年間労働大臣(現・厚生労働大臣)を歴任融資の条件は、従業員の50%以上が障害者であり、なおかつその過半数が重度の障害者であるというものです。借金してどう返済するのかと考えましたが、その前に禅寺のご住職のお話を聞いていたでしょう。一人でも多く雇用したいという思いでやっていたときでしたから、「よし」と。手をあげてつくったのが今の工場です。
人を仕事にあわせるのではなく、仕事を人にあわせる
────障害を持つ方を多く雇用をすることに、不安や迷いはお感じになりませんでしたか。
知的障害者のことを、「精神のおかしな人」と思っていたくらいの我々ですからね。スタートのころは、障害者福祉の専門家の力を借りた方がいいだろうと、そういった経験のある方に来ていただいたんです。ところが、採用した子たちも進歩しませんでしたし、専門家は「このIQでは、この作業は難しい」と言うんですね。
────数字で判断されるのですね。
しかし、雇用してしまったわけですから、これはもう自分たちで何とかしようと。彼らが一人で物事を判断して行動するのはどういうときなのかを考えて、ヒントになったのが交通信号です。彼らは文字が読めなくても、ちゃんと横断歩道を渡って会社までやってきます。そうか、この子たちは色の識別はできるんだ、と。それを、材料の計量に応用したのです。
彼らは、材料が入っている紙袋に印刷してある文字も、「キログラム」といった単位も理解できません。そこで、材料を大きな缶に入れてフタに色を塗り、「赤いフタの缶の材料を量るときは赤いおもり、青いフタの缶には青いおもりを使うんだよ」と。そして「5つ数えてもはかりの針がまん中で止まったままなら、はかりから下ろしていいよ」と。こう工夫したわけです。
この作業を、集中力がなくて周りが手を焼いていたある知的障害者の従業員に任せたところ、一所懸命にずっとやっているんですね。誤差が少しでもあれば品質に影響しますから、職員がこまめに見に行っては、「上手にできているね」「ちゃんと5つ数えているね」と、褒めていたようです。それもあってか、あっという間に量ってしまい、「もっとやっていいですか」と言うんです。
理解力に合ったやり方を考えて、ご住職が言われたように褒めてあげれば、こんなにも一所懸命になるのかと。そのことに気づいてからは、材料を練る時間を計るのに砂時計を使うなど、工程をさまざまに工夫するようになりました。そうすれば集中して一所懸命にやるようになりますから、生産性は健常者とそう大きく変わらないんです。
 *
* *
*
(写真左)材料が入っている缶のフタとおもりを同じ色に塗り、文字や数字が理解できなくても計量できるように工夫。
(写真中)材料の撹拌や加熱の時間は、砂時計で計測。時計が読めなくても、作業時間を正確にコントロールできる。
(写真右)箱詰作業では、数をかぞえる負担を減らすため、所定の本数が載るトレーを開発。その次には、作業を余分に覚えた知的障害者の社員を「班長」にしました。彼らは、仲間にはとても親切です。その長所をうまく引き出して、新しく入ってきた社員に仕事を教えることを任せたんです。そうすれば、健常者の指導員を置く必要がありませんから、余分な人件費もかからない。仕事の生産性も、健常者に劣りません。ですから、日本理化学はここまでやってこられたのだろうと思います。
────そういった工程の工夫をされるようになったのは、最初に2人の方を雇用されてから、どれくらい経たれたころのことですか。
4、5年目くらいですね。人数が増えますと、一所懸命やってくれる人もいますが、集中力がなくて困る人もいる。それで何とかしなくてはいけなくなって、工夫が生まれたのです。学校で計量を教えるなら、はかりの原理を理解させて、目盛りを読むための文字や数字も覚えさせますね。しかし、会社では文字が読めても読めなくても、結果がちゃんと出ればいい。そう発想を変えて、本人の理解力に工程を合わせれば、そんなに大変なことではないんですよ。
天の神様は、誰にでも「世の役に立つ才能」を与えてくれている

────社員が「仕事ができない」「成長しない」というのは、仕事の与え方に問題があるということですね。このお話は知的障害者の方々だけでなく、私たちすべてに当てはまるように思います。
ある大手企業で講演させていただいたときも、同じことを言っておられましたね。このことを私に気づかせてくれたのは、実は小学5年生のお子さんなんです。学校の宿題でチョークの作り方をレポートするために、お母さんと2人で見学に来られましてね。有名な私立小学校の生徒さんでしたから、見学の後にこう話したんです。「君みたいな優秀な学校を卒業した子は一人もいなくて、みんな文字や数がわからない人たちなんだよ」と。そのときは驚いた様子でただ聞いていましたが、後日彼から届いた礼状に、こんな言葉が書かれていました。「天の神様は、どんな人にでも世の中の役に立つ才能を与えてくださっているんですね」と。
ただ、この子たちも才能が最初からあったわけではありません。彼らが役に立てるような段取りを周りの人がしてあげて、本人も役に立てることが幸せだから一所懸命にやる。それが積もり積もって、才能になるんです。ですから、周囲の役割もとても大切です。小学5年生のお子さんがくれたこの2つの気づきが、日本理化学が今ある原点なのです。
「人のために一所懸命にやっていると、多くの人が応援してくれる」。大山会長はこれまでの道のりをこう振り、「利他の経営」が企業存続の秘けつであると語ります。この言葉にはどのような思いが込められているのか、後編では社会や企業のあり方について伺います。
-

聞き手:OBT協会 伊藤みづほ
OBTとは・・・ 現場のマネジャーや次世代リーターに対して、自社の経営課題をテーマに具体的な解決策を導きだすプロセス(On the Business Training)を支援することにより、企業の持続的な競争力強化に向けた『人財の革新』と『組織変革』を実現している。
*続きは後編でどうぞ。
「人を仕事に」ではなく、「仕事を人に」あわせて生産性を高める逆転の発想(後編)
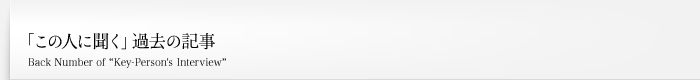
- 株式会社JR東日本テクノハートTESSEI
専務取締役 矢部 輝夫さん - 経営改革は、実行する「現場の実態」を把握して、初めて実現する(前編) - 千葉夷隅ゴルフクラブ
総支配人 岡本 豊さん - 企業の競争優位性は結果指標ではなく
それを生み出す組織の強さ、社員のモチベーションに規定される(後編) - 千葉夷隅ゴルフクラブ
総支配人 岡本 豊さん - 企業の競争優位性は結果指標ではなく、
それを生み出す組織の強さ、社員のモチベーションに規定される(前編) - 七福醸造株式会社
代表取締役会長 犬塚 敦統さん - 【事業で差別化しうるのは唯一人財のみ】
人が気づき、変わる瞬間とは(後編) - 七福醸造株式会社
代表取締役会長 犬塚 敦統さん - 【事業で差別化しうるのは唯一人財のみ】
人が気づき、変わる瞬間とは(前編) - 株式会社キングジム
代表取締役社長 宮本 彰さん - 【事業で差別化しうるのは唯一人財のみ】
知というアイデアを製品化し、利益に結びつける組織とは(後編) - 株式会社キングジム
代表取締役社長 宮本 彰さん - 【事業で差別化しうるのは唯一人財のみ】
知というアイデアを製品化し、利益に結びつける組織とは(前編) - 東海バネ工業株式会社
代表取締役社長 渡辺 良機さん - 【事業で差別化しうるのは唯一人財のみ】
やること、やらないことを決める
競争優位を明確にすることは、社員育成にもつながる(後編) - 東海バネ工業株式会社
代表取締役社長 渡辺 良機さん - 【事業で差別化しうるのは唯一人財のみ】
やること、やらないことを決める
競争優位を明確にすることは、社員育成にもつながる(前編) - 人とホスピタリティ研究所所長
前リッツ・カールトン日本支社長
高野 登さん - 【事業で差別化しうるのは唯一人財のみ】
成熟化社会は、ホスピタリティが鍵となる(後編)